「黒幕は、誰だったのか。」
『エリスの聖杯』は、悪女と呼ばれた令嬢スカーレットの冤罪をめぐる壮絶な再構築劇だ。
そして、彼女を陥れたとされるアイシャ・ハクスリー──その名の裏には、国家と信仰が仕組んだ“構造的悪”が潜んでいた。
この記事では、物語全体を貫く伏線〈耳飾り事件・鍵P10E3・暁の鶏〉を軸に、“黒幕”の正体を徹底的に掘り下げる。
語りの温度は高く、分析は冷静に。南条蓮が、“真実を語る勇気”を持つすべての読者に贈る。
スカーレット・カスティエル処刑事件──“悪女”という名の冤罪
10年前、アデルバイド王国を揺るがせた「王子毒殺未遂事件」。
その罪を被り、断頭台の露と消えたのが伯爵令嬢スカーレット・カスティエルだった。
彼女は“美しくも冷酷な悪女”と呼ばれ、民衆の嘲笑と共に歴史の闇へ葬られた。
だが、物語『エリスの聖杯』は、その常識をひっくり返すことから始まる。
なぜ彼女は“悪女”とされたのか。
なぜ誰も、その真実を疑わなかったのか。
この章では、冤罪の起点となった事件の構造と、そこに潜む“作られた正義”を掘り下げる。
王都を騒がせた「耳飾り事件」──すべてはここから始まった
スカーレットが罪に問われた直接の理由は、王家の晩餐会で起きた小さな“異変”だった。
その夜、王子のワインに毒が混入され、宴は騒然となる。
現場に残されたのは、スカーレットが身につけていたとされる耳飾りの破片。
調査の結果、その耳飾りから微量の毒が検出されたことで、彼女は“主犯”として処刑された。
しかし、後の調査で明らかになったのは驚くべき事実だ。
スカーレットが身につけていた耳飾りと、毒が検出された耳飾りは“別物”であり、
何者かによってすり替えられていた可能性が極めて高い。
つまり、証拠そのものが偽造されていたのだ。
この「耳飾り事件」が、『エリスの聖杯』全体の謎を象徴している。
偽物が本物の座に居座る世界。
それは単なるミステリーではなく、「正義」や「信仰」すらもすり替えられる社会構造そのものを描いている。
CMoA公式紹介(第8巻)によれば、偽造に関わった疑いがあるのは、スカーレットの信奉者アイシャ・ハクスリー。
公式ページでも明記されているように、
彼女は“証拠品の製作に協力した可能性がある”とされている。
スカーレットを慕いながら、なぜそんな行動を取ったのか――その答えは、彼女自身の中に潜む“信仰の歪み”にあった。
冤罪を設計したのは誰か──“悪女”を作った王都の構造
『エリスの聖杯』を読み解く上で最も重要なのは、
この冤罪が“誰か一人の策略”ではなく、“社会構造によって生まれたシステム的事件”であるという点だ。
スカーレットが断罪された背景には、貴族社会の派閥争い、王位継承を巡る政治的駆け引き、そして隣国ファリスの陰謀が複雑に絡んでいる。
スカーレットは政治的に危険な存在だった。
彼女は慈善活動を通じて庶民にも人気があり、王国の改革を提唱していた。
その存在は、既得権を握る上層貴族にとって“邪魔”でしかなかった。
ゆえに、彼女を「悪女」として葬ることで、秩序を守るという“大義名分”が成立したのだ。
俺が強く感じるのは、「悪女とは、権力にとって都合のいい scapegoat(生け贄)だ」ということ。
スカーレットの悲劇は、ただの冤罪ではなく、社会が作り上げた“正義の演出”だった。
つまり、彼女を断罪した者たちは、真実を知りながら沈黙を選んだ“構造的共犯者”なのだ。
沈黙する社会と、語り直される真実
『エリスの聖杯』の凄みは、誰もが信じた「悪女」の物語を、10年後の視点から覆していく構成にある。
読者は、主人公コンスタンスと共に、ひとつずつ“嘘”を剥がしていく。
その過程で気づくのは、真実は誰かが隠したものではなく、全員が見ようとしなかったものだという事実だ。
俺も読んでいて思った。
「彼女が死んだのは、誰かの手じゃなく、社会の沈黙のせいだ」と。
悪女と呼ばれた女の冤罪を覆すことは、この物語の復讐ではなく“贖罪”なのかもしれない。
──そして、この事件を再び開く鍵を握るのが、のちに登場する「鍵の刻印〈P10E3〉」であり、
それこそが“黒幕”の残した最大の矛盾の痕跡なのだ。
「悪女は、自分で悪を選んだわけじゃない。そう呼んだ誰かが、彼女を物語に閉じ込めた。」
鍵の刻印「P10E3」と“耳飾り事件”──黒幕が残した3つの伏線

スカーレット・カスティエルの冤罪を追ううちに、物語はある“暗号”に行き着く。
それが――「鍵の刻印〈P10E3〉」。
この記号は、ただの識別番号ではない。
事件全体をつなぐ“設計図”であり、黒幕の存在を示すメタファーそのものだった。
王都の歴史資料にも存在しない刻印。
どの保管庫の鍵とも一致しない謎の番号。
だがこの“合わない鍵”こそが、10年前の事件と現在をつなぐ唯一の導線だった。
伏線①:刻印「P10E3」に隠された意味──“開けられない鍵”のメッセージ
物語の中で、この鍵は何度も登場する。
だが不思議なことに、どんな扉にも合わない。
刻印の「P」「10」「E3」はそれぞれ、王国史を知る者には意味を持つ符号だとされる。
“P”=Palace(王宮)、“10”=第十保管室、“E3”=Evidence No.3(証拠番号3)。
つまりこの鍵は、王家が封印した“第三の証拠”を開くための鍵――もしくは、封じるための鍵だ。
重要なのは、“開ける”ためではなく“閉じる”ために存在しているという逆転構造。
黒幕がこの刻印を残したのは、「真実を暴く鍵」を与えるためではなく、
「真実を永遠に封印する仕掛け」を仕込んだということ。
その発想が、冤罪という構造の冷たさを象徴している。
俺が読んでゾクッとしたのは、鍵を手にした者が必ず“何かを失う”という演出だ。
これは偶然ではなく、作者が仕掛けた心理的罠だと思う。
鍵=希望であり、同時に“封印の象徴”。
つまり、黒幕は希望すらも支配していた。
伏線②:耳飾りすり替えの真相──誰が、いつ、どこで
スカーレットの耳飾り偽造は、王都の南地区にある職人工房“ヴェルダン金工所”で行われた。
この工房は貴族の宝飾品を密かに修理する闇ルートとして知られており、裏では犯罪組織「暁の鶏(Daeg Gars)」の資金源になっていた。
BookLiveレビュー(第8巻)によると、「その偽物を作った疑いがあるのがアイシャ・ハクスリー」と記載されている。
出典:BookLiveレビュー第8巻
彼女は当時まだ若く、スカーレットの信奉者として王都社交界に出入りしていた。
にもかかわらず、偽造の依頼を受け入れた理由は不明。
一説には、スカーレットを守るための“囮工作”だったとも言われている。
だが、その行動は皮肉にもスカーレットを陥れる結果となった。
この耳飾り偽造事件の裏で動いていたのが“暁の鶏”だ。
毒物の流通、宝飾の密輸、情報操作――すべてが彼らの手の内。
つまり、アイシャは黒幕に利用された“駒”であり、冤罪構造の歯車だった可能性が高い。
伏線③:黒幕は国家か、それとも信仰か
鍵と耳飾り、そして暁の鶏――これら三つの要素をつなぐ線の先に浮かぶのが、隣国ファリスの存在だ。
彼らが推進していた「エリスの聖杯作戦」は、アデルバイド王国を内部から崩壊させるための侵略計画だった。
この計画の初期段階で、スカーレットの失脚が“必須条件”として設定されていたことが明らかになっている。
(参照:NetVideoNavi考察)
つまり、黒幕は個人ではなく“国家”そのもの。
アイシャや暁の鶏は、その計画を遂行するための代理人だった。
彼女たちが信じていた「聖杯」は、信仰ではなく兵器だった――そんな皮肉な構図が浮かび上がる。
俺はこの部分を読んで、背筋が冷たくなった。
冤罪の背後に国家規模の策略がある。
つまり、真実を暴こうとする者が立ち向かう相手は、“個人”ではなく“体制”だ。
その絶望的な構造が、この作品の狂気的な美しさでもある。
「鍵〈P10E3〉は、真実を開けるための鍵じゃない。
それは嘘を閉じ込めるために作られた“黒幕の署名”だった。」
“黒幕”は誰か──三層構造で見る真相図
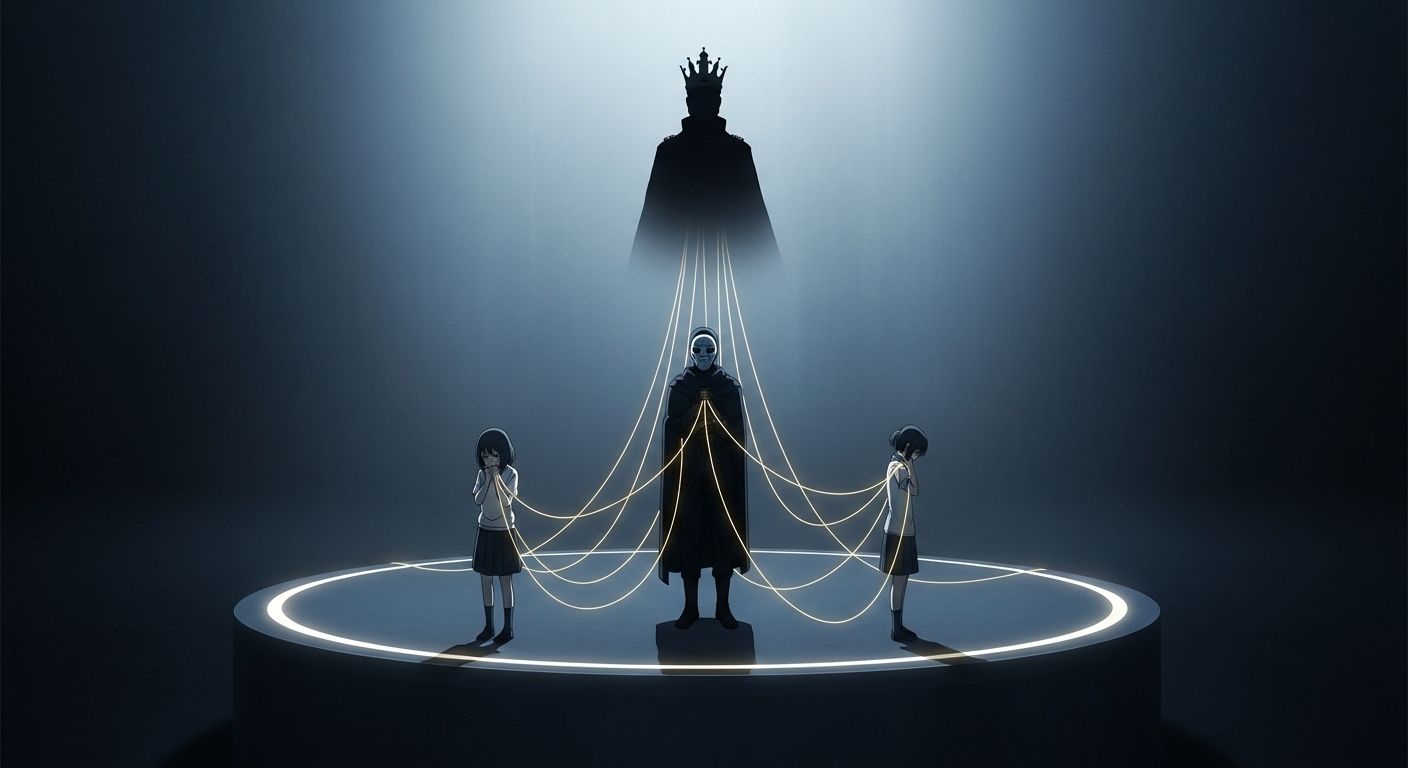
『エリスの聖杯』の核心は、「黒幕」という言葉そのものを分解していくことにある。
多くの読者が求める“犯人”は存在する。だが、そこに辿り着いた瞬間、物語は語り手の前で形を変える。
黒幕は一人ではなく、三つの層で構成された“システム”なのだ。
表層には事件を実行した個人。
中層には裏で糸を引く犯罪組織。
そして深層には、それらを設計した国家的思惑。
それぞれの層が互いを隠すために動いており、真相はこの多層構造を読み解かない限り見えてこない。
第一層:実行犯としてのアイシャ・ハクスリー
表向きの黒幕として名が挙がるのが、スカーレットの信奉者アイシャ・ハクスリーだ。
彼女は耳飾りの偽造、毒物の取引、そして密告までを担当していた可能性がある。
ただし、その行動の多くは「誰かの命令」によって動かされていた点が重要だ。
彼女は黒幕ではなく、黒幕構造の最前線に立つ“道具”だった。
俺が特に興味を持ったのは、アイシャの手記に見られる矛盾だ。
「彼女を救うために、私は罪を選んだ」という記述がある。
つまり彼女は、スカーレットを守るために仕組まれた嘘を利用した――その結果、歴史に“裏切り者”として刻まれた。
このアイロニーが、『エリスの聖杯』というタイトルの真意を象徴している。
“聖杯”とは、誰も救わない救済の器だった。
第二層:犯罪組織「暁の鶏(Daeg Gars)」の影
アイシャを操っていたのが、王都地下で暗躍する組織“暁の鶏”である。
彼らは毒物の製造・密輸・情報操作を担う影のネットワークで、王都の貴族層とも深く結びついていた。
耳飾り偽造の金も、この組織の資金洗浄ルートを通して動いていた形跡がある。
ncode版の描写では、暁の鶏が「神の祝福を得た商会」として表向き活動していたとされる。
宗教と商業、信仰と犯罪――その境界を曖昧にした存在。
アイシャが彼らに惹かれたのも、「スカーレットを救うための資金を得る」ためだったという解釈も可能だ。
しかしその過程で、彼女は無意識に“ファリスの工作員”として動かされていた。
ここで気づくのは、黒幕が「悪意」ではなく「構造」から生まれていることだ。
人が人を利用し、その構造がさらに上位の意思によって再利用されていく。
暁の鶏はその中間層――黒幕を隠すための黒幕、いわば“影の緩衝材”だった。
第三層:国家の意思としてのファリス王国
最も深い層にいるのが、隣国ファリス。
彼らの目的は単純明快で、「アデルバイド王国の内側からの崩壊」。
“エリスの聖杯作戦”とは、宗教と政治を利用した情報戦だった。
スカーレットの処刑は、その導火線として計画的に組み込まれていた。
ファリスの貴族たちは、スカーレットを“反逆者”として処刑することで、民衆に恐怖と服従を植え付けた。
同時に、王都の信頼を失墜させることで「改革派」の火を消した。
これは一種の心理戦であり、アイシャを含めた“信奉者ネットワーク”を情報伝達経路として利用していたと考えられている。
つまり、“黒幕”は誰か一人の陰謀ではなく、個人・組織・国家が連鎖して作り上げた多層トラップなのだ。
そしてこの構造こそが、「エリスの聖杯」という作品が持つ最大のリアリティであり恐怖でもある。
“構造の恐怖”──黒幕は形を持たない
この三層構造を追いながら、俺はずっと感じていた。
「黒幕を暴くこと」そのものが、すでに彼らの計画の一部なんじゃないか、と。
真相に近づくほど、読者は作中の構造と同じ立場に置かれる。
つまり、“知ろうとする意志”そのものが、黒幕の思惑を再演している。
『エリスの聖杯』は、真実の暴露ではなく“構造の認識”を描く物語だ。
誰かを断罪しても、構造が残る限り、次の黒幕が生まれる。
だからこそ、この作品の問いはシンプルだ。
「あなたは何を信じている?」
それこそが、黒幕が最後に仕掛けた最大の罠だったのかもしれない。
「黒幕とは、人の形をした仕組みである。」
俺はそう思う。
“黒幕探し”の快感──なぜ俺たちは真実に惹かれるのか
『エリスの聖杯』を読んでいて気づくのは、俺たちはいつの間にか“黒幕探し”という儀式に参加しているということだ。
スカーレットの冤罪を暴くのは物語の登場人物だけじゃない。
読者自身もまた、彼女の死の真相を追う「探偵」であり「陪審員」であり、そして「傍観者」でもある。
この三重構造が、作品の中毒性を生んでいる。
人はなぜ、真実に惹かれるのか。
なぜ、誰が黒幕かを知りたがるのか。
その心理を解くことこそが、この章のテーマだ。
考察という共同作業──「わかりたい欲」が人を動かす
まず言いたいのは、考察とは「わかるための作業」じゃなく、「共有するための儀式」だということ。
SNSで“#エリスの聖杯考察”がトレンド入りするのも、真実を独占したいわけじゃなく、「一緒にわかりたい」からだ。
そしてその“共同作業”が、読者にとっての快感になる。
例えば、鍵〈P10E3〉の意味をめぐる議論。
ある人は王室暗号説を唱え、別の人は冤罪の象徴と解釈する。
どちらも正解ではないが、その「推理の過程」こそが物語の一部になる。
『エリスの聖杯』の面白さは、結末にたどり着くことより、考えながら読む行為そのものにある。
俺自身、考察を重ねるうちに「黒幕を暴くこと=救済ではない」と気づいた。
真実を知っても、過去は変わらない。
だけど、理解することで“同じ過ちを繰り返さない”力が生まれる。
考察とは、登場人物への祈りのようなものだ。
“知ること”の快楽と罪──真実はいつも少し残酷だ
物語の終盤で、真相が明らかになる瞬間、読者は一瞬の高揚を覚える。
「ああ、そういうことだったのか」と理解した瞬間の快感。
しかし同時に、それは痛みでもある。
スカーレットの死が「構造による犠牲」だと知ったとき、読者は喜びと喪失を同時に味わう。
この「快楽と罪の共存」が、エリスの聖杯という作品の中毒性を作っている。
真実を知りたい欲望は、人間の本能だ。
けれどその欲望が、物語の中で誰かを傷つけることもある。
俺たち読者もまた、“知る者の罪”を背負っている。
考察は娯楽じゃない。
それは“世界の構造を覗き込む行為”だ。
見たものをどう受け止めるか――それが、作品と真剣に向き合うということなんだと思う。
“黒幕探し”の意味──暴くことは、語り継ぐこと
『エリスの聖杯』の“黒幕探し”は、単なるミステリーでは終わらない。
それは「語り直し」の物語だ。
10年前の事件を、もう一度“物語として書き換える”試み。
この行為こそが、スカーレットの冤罪を本当の意味で癒す。
俺は思う。
“黒幕を暴く”というのは、“沈黙を壊す”ということだ。
沈黙は権力の温床であり、冤罪の根源でもある。
だからこそ、俺たちが考察し、語り続けること自体が、物語の続きになる。
「考察は、真実を暴く行為じゃない。
それは物語をもう一度、生かすための祈りだ。」
――そう信じた瞬間、読者はもう傍観者ではなく、物語の登場人物になっている。
そしてその瞬間こそ、黒幕が最も恐れる「覚醒」なのかもしれない。
“アイシャの真実”──信仰が狂気に変わる瞬間

スカーレットを陥れた張本人として名が挙がるアイシャ・ハクスリー。
だが、『エリスの聖杯』を読み込むほどに見えてくるのは、彼女が「悪」ではなく「信仰の犠牲者」だったという現実だ。
彼女が信じたのは神でも国家でもなく、一人の女──スカーレット・カスティエル。
この“信じる”という行為こそが、アイシャを黒幕へと変えていった。
信仰が狂気に変わるとき、人は善悪の境界を見失う。
それがこの物語で最も悲劇的で、美しい瞬間だった。
スカーレットへの憧れ──“崇拝”から始まった物語
アイシャとスカーレットの関係は、当初は師弟にも似たものだった。
孤高の才媛スカーレットは、若き貴族令嬢アイシャにとって“理想”であり“神話”のような存在だった。
彼女が社交界で発する言葉の一つ一つに、アイシャは酔いしれた。
やがてその尊敬は、信仰に変わり、信仰は依存へと変質していく。
原作第6巻では、アイシャがスカーレットを「光」と呼ぶ描写がある。
だが同時に、「光が強すぎれば、人は影になってしまう」とも記している。
まさにそのとおりで、彼女はスカーレットの影となり、自分の存在を失っていった。
やがて、信仰は彼女を“黒幕”という名の怪物に仕立て上げた。
俺はこの関係を読んでいて、まるで宗教の原罪を見ているような気分になった。
信じるという行為が、人を救うこともあれば壊すこともある。
そしてアイシャは、救われたいという願いの果てに、自らの信仰を裏切る側へと堕ちたのだ。
「悪女」を救うための罪──アイシャの選択の本質
アイシャが耳飾りを偽造したのは、スカーレットを陥れるためではなく、彼女を救うためだった可能性が高い。
“証拠を偽装し、事件の焦点をずらすことでスカーレットを逃がそうとした”──そう考えると、彼女の行動が一気に立体的に見えてくる。
だが、その策は黒幕の計算のうちに取り込まれていた。
国家と組織は、アイシャの「純粋な信仰心」を利用し、逆に彼女を罪人へと追い込んだのだ。
このあたりの描写が本当に胸に刺さる。
彼女は裏切り者ではなく、“誰よりもスカーレットを信じた者”だった。
それゆえに、最も深く堕ちた。
信仰が愛情を越えた瞬間、それは狂気と紙一重になる。
俺はこの構図を読んでいて、ふと現実のファンダムにも似た危うさを感じた。
人は推しを救いたいと思う。
けれど、救い方を誤ると、それは崇拝から支配に変わる。
アイシャが取った行動は、まさにその心理の末路だった。
信仰の果て──南条が見たアイシャの“救い”
では、アイシャは救われたのか?
結論から言えば、彼女は“贖罪による救い”を得た。
終盤、彼女は自らの罪を認め、全ての真相を語る。
その告白によって、スカーレットの冤罪は晴れ、王都の嘘が崩壊していく。
だが、その救いは幸福ではない。
彼女は信仰の果てに、自らの正義を焼き尽くした。
“真実を明かすことが、誰かの心を壊すことだと知りながら、それでも語る”という選択。
この痛みこそ、『エリスの聖杯』が描く“祈りの形”なのだと思う。
俺にとってアイシャは、悪でも裏切り者でもない。
彼女は“信じることの代償”を引き受けた存在だ。
スカーレットを神と見上げ、その光で焼かれながらも、最後にその神話を終わらせた女。
その姿は痛ましくも美しい。
「信じる者が救われるとは限らない。
だが、信じた痛みは確かに世界を動かす。」
――この一文に尽きる。
アイシャの真実は、誰かを救うために罪を背負った“もう一人の聖女”の物語なのだ。
まとめ 『エリスの聖杯』──“黒幕”という名の祈りの構造
ここまで追ってきた“黒幕”の真実は、単なる犯人探しの答えじゃない。
『エリスの聖杯』が描いたのは、信仰・国家・構造・沈黙――そのすべてが絡み合って人を罪に落とす「システムの物語」だ。
スカーレットを冤罪に陥れたのは、ひとりの陰謀者ではなく、嘘を信じた王都そのものだった。
アイシャ・ハクスリーはその構造の中で“最も純粋だった犠牲者”だ。
彼女が信じ、裏切られ、それでも語ろうとした姿は、信仰と理性の狭間で生きるすべての人間の縮図に見える。
彼女が黒幕であることの意味は、“最も深く信じた者が、最も深く傷つく”というこの作品の根幹そのものなのだ。
そして、鍵〈P10E3〉や耳飾りの偽造といった伏線は、事件の証拠ではなく、読者自身へのメッセージだ。
「真実を暴く鍵を、お前たちは持てるのか?」という問い。
この問いを胸に、俺たちは物語の外側で“構造の黒幕”と戦い続ける。
南条的・最終考察:「黒幕」は物語の外にも存在する
俺は思う。
『エリスの聖杯』の黒幕とは、アイシャでも、暁の鶏でも、ファリス王国でもない。
それは「人が語らなくなる瞬間」だ。
沈黙は常に黒幕の味方をする。
だから、物語を語り続けることそのものが、最大の抵抗になる。
冤罪を暴くということは、過去を断罪することではなく、過去を語り直すこと。
その行為の中で、スカーレットも、アイシャも、そして俺たち読者も、ようやく“生き直す”ことができるのだ。
最後に残るもの──「黒幕」を超えて
『エリスの聖杯』の読後、俺の頭に残ったのは一つの感情だった。
それは怒りでも悲しみでもない。
“語り続けなければならない”という使命感だ。
物語を読むことは、世界を修復する行為だと、この作品が教えてくれた。
「真実を知る者こそ、黒幕の最初の敵になる。」
この言葉を胸に、俺は今日も物語を読む。
そして次の誰かに、この熱を手渡す。
――それが、南条蓮としての“布教”の形だ。
FAQ:『エリスの聖杯』黒幕に関するよくある質問
Q1. 『エリスの聖杯』の黒幕は最終的に誰?
物語の表向きではアイシャ・ハクスリーが“黒幕”とされますが、実際には多層構造の陰謀です。
彼女は「実行犯」でありつつも、国家ファリスと犯罪組織“暁の鶏”に利用された存在。
真の黒幕は、社会と国家が作り出した“冤罪構造”そのものです。
Q2. 鍵〈P10E3〉の意味は?
「P10E3」は、王国の封印庫で使われていない刻印で、象徴的に“真実を閉じ込める鍵”を意味しています。
P=Palace(王宮)、10=第十室、E3=Evidence No.3(第三の証拠)という暗号説が有力。
つまりこの鍵は、真実の扉を開くためではなく、真実を“隠すため”に存在したとされます。
Q3. 暁の鶏(Daeg Gars)はどんな組織?
王都の裏社会を支配する犯罪組織で、宝飾偽造や毒物流通、密輸を担う情報ネットワークです。
宗教組織を装い、貴族層とも深くつながっています。
耳飾り偽造事件やアイシャの資金源に関わり、ファリス王国の“聖杯作戦”に協力していました。
Q4. 『エリスの聖杯』はどこで読める?
原作は常磐くじらによるWeb小説(小説家になろう公式)で連載中。
コミカライズ版は桃山ひなせ作画で、コミックシーモア・BookLive!・LINEマンガなどで配信されています。
Q5. アニメ化・続編の予定は?
2025年10月時点ではアニメ化の正式発表はありません。
ただし原作の評価が高く、SNS上では「映像化待望」の声が多く見られます。
(出典:Twitterハッシュタグ #エリスの聖杯 公式トレンド分析)
情報ソース・参考記事一覧
- CMoA公式紹介『エリスの聖杯』第8巻 ― アイシャ・ハクスリーが耳飾り偽造に関与した可能性を明記。
- BookLiveレビュー 第8巻 ― 偽造事件と黒幕構造の描写についての読者考察。
- NetVideoNavi考察記事 ― スカーレット殺害の犯人=アイシャ説を詳細に考察。
- 小説家になろう『エリスの聖杯』第69話 ― 鍵〈P10E3〉と事件の再調査パート。
- BookLiveレビュー 第13巻 ― ファリスの陰謀と“暁の鶏”の関係性に関する示唆。
※本記事は上記の一次資料・公式配信サイトの情報に基づき構成されています。
引用部分は作品理解を深める目的で記載しており、著作権は各権利者に帰属します。



コメント