「正義って、勝った奴の名前がそう呼ばれるんだ」──。
その一言で始まる『青のミブロ』は、幕末という混沌の時代に生きる少年たちが“理想”と“現実”の狭間でもがく物語だ。
史実の新選組を土台にしながらも、中心にいるのは誰の記録にも残らない一人の少年・にお。
彼の“青い信念”が、血と涙に染まりながらも決して濁らないその姿に、俺は息を呑んだ。
この記事では、第一部完結までの物語と芹沢鴨暗殺の真相、そして“青”という色に込められた意味を徹底解説する。
2025年12月から放送されるアニメ第2期「芹沢暗殺編」に向けて、この作品の魂をもう一度、言葉で辿っていこう。
『青のミブロ』──正義の色が交わる夜
幕末。刀の音が風よりも先に鳴る時代。
『青のミブロ』は、その混沌の只中で「正義」という言葉を何度も裏切り、何度も信じ直す少年たちを描いた作品だ。
作者・安田剛士(『ダイヤのA』の作画でも知られる)が、これほどまでに“熱”を込めたのは、この物語が単なる新選組再演ではなく、「己の正義を定義し直す物語」だからだ。
史実の新選組をベースにしながらも、登場人物たちは歴史の枠を飛び越え、まるで現代の俺たちにも突きつけてくるように問う──
「お前の正義は、誰のためのものだ?」
におの視点で描かれる“青の物語”は、まるで読者自身の心を映す鏡のようだ。
彼が剣を抜くたびに、俺たちは心のどこかで震える。
なぜならこの作品は、「信じたい理想」と「抗いがたい現実」の衝突を、どこまでも真正面から描いているから。
そして俺が惹かれてやまないのは、『青のミブロ』が「血と青春を同列に語る稀有な作品」だという点だ。
正義が人を救う瞬間もあれば、正義が人を殺す瞬間もある。
そのすべてを“青”という一つの色に込めて描くその筆致には、安田剛士の覚悟すら感じる。
雨の夜に交わる、正義と誠
『青のミブロ』の物語は、京都の雨の夜から始まる。
路地裏に灯る行灯の光、濡れた石畳、どこか遠くで響く刀の音。
その空気感の描写がまず圧倒的で、まるで映画のような演出が施されている。
少年・におは、そんな混沌の中で「正義」という言葉にすがるように生きている。
だが、彼が出会うのは土方歳三や近藤勇、そして沖田総司といった“歴史の化け物たち”だ。
彼らの正義は、におが信じていたものとはまるで違う。
土方の言葉──「正義なんざ、勝った奴の名前がそう呼ばれるんだ」──は、少年の胸に刃のように突き刺さる。
この瞬間、におは悟る。
「自分の信じる正義は、誰にも守ってもらえない」ということを。
俺が思うに、ここが『青のミブロ』の最初の肝だ。
他の歴史漫画は“正義を貫く”ことを描くが、この作品は“正義を疑う”ところから始まる。
その発想が、圧倒的に現代的で、同時に痛いほどリアルなんだ。
におの迷いは、俺たちが日々の中で感じている「本当の正しさはどこにあるのか」という葛藤そのものだ。
土方は冷徹だが優しさを捨てていない。
近藤は理想を抱きながらも現実に踏み潰されることを恐れない。
そしてにおは、その狭間で震える“青い正義”の象徴として存在する。
このトライアングル構造が、物語の全編を通して読者を引きずり回す。
「青」という色に込められた意味
『青のミブロ』における“青”は、決して爽やかさや清らかさの象徴ではない。
むしろそれは、濁り、迷い、葛藤の中に宿る強さの色だ。
作中では、におの髪や瞳の色、空や雨の描写など、至るところで青が用いられている。
この色彩設計の一貫性が、作品全体に“詩”のような統一感を与えている。
沖田総司のセリフ「青ってさ、混じると何にでも染まる。でも、澄ませば芯が見える。」は、この作品のテーマそのものだ。
人は他人の意見や社会の価値観に簡単に染まる。
だが、そこから澄み渡らせ、自分の“芯”を見つけ出すには、血のような痛みが必要になる。
におが戦いの中で流す涙と血は、その澄みの過程だ。
俺はここに、“現代のオタク世代”が共感できるメッセージを感じる。
SNSや社会の空気に飲まれながらも、「俺はこれが好きだ」と胸を張って言える芯。
『青のミブロ』の青は、まさにその“好きと信念の境界線”の色なんだ。
それがこの作品を単なる歴史アクションではなく、“魂のドキュメント”にしている。
読後、俺が一番感じたのは、「この物語を語ること自体が布教になる」という感覚だ。
におの青に、自分の青を重ねる人が確実に増えている。
この導入だけで、もう布教したくてたまらなくなる。
いや、マジでこの作品は、語らなきゃもったいない。
登場人物と基本設定:ミブロとは何者たちか

『青のミブロ』という作品を語る上で、避けて通れないのが「ミブロ=壬生浪士組」という存在だ。
幕末という歴史の中で、血と誠を背負った彼らが、どんな“魂の物語”を紡いでいくのか。
その理解があるだけで、におたちの戦いが何倍も深く感じられる。
俺自身、最初は「どうせまた新選組モノか」と思っていた。
だが、読んでみたらまるで違う。
これは、史実という枠の中に“現代の若者の生き様”を埋め込んだ、まさに「生きる哲学漫画」だった。
壬生浪士組=ミブロの成り立ちと理念
ミブロ(壬生浪士組)は、幕末の京都で結成された浪士集団。
後に「新選組」と改名されることになる彼らは、幕府の治安維持のために設立された、いわば時代の歯車の一つだ。
しかし『青のミブロ』が描くのは、単なる歴史的事実ではない。
この作品では、ミブロは「理想を抱きながらも、理想に裏切られた者たちの集団」として描かれている。
近藤勇は「正義を形にする力」を信じ、土方歳三は「誠を貫くために冷酷さを選んだ」。
その間で揺れる芹沢鴨は、まるで“組織という怪物”そのものの化身だ。
彼は暴虐で、野心的で、破滅を知りながらも突き進む。
だが同時に、彼の中にも“正義を信じた少年の残滓”が見え隠れするのが恐ろしいほど人間臭い。
そして、その中心に放り込まれたのが、オリジナルキャラの「にお」だ。
彼は史実には存在しない。
だが、だからこそ読者がこの作品に感情移入できる“視点そのもの”になっている。
におの視点で見るミブロは、理想と現実、正義と腐敗が複雑に絡み合う戦場そのものだ。
俺が特に痺れたのは、作中で描かれるミブロの「人間臭さ」だ。
彼らは神話じゃない。
どれだけ立派な旗を掲げても、内側は嫉妬と憎悪と未練でぐちゃぐちゃだ。
そのリアルさこそが、『青のミブロ』が“生身の正義”を描けている理由だと思う。
主要キャラクター解説と人間関係の軸
ここからは、物語の中心人物たちを整理しておこう。
キャラそれぞれの信念や矛盾を理解しておくと、後半の暗殺編やにおの正体がより深く刺さる。
◆にお(主人公)
白髪と青い瞳を持つ少年。
貧しい暮らしの中で理不尽に苦しみ、それでも「正義を信じたい」と願い続ける。
物語を通して彼は、土方や近藤から「現実の正義」を突きつけられ、少しずつ理想と現実の間で変化していく。
“青”は彼自身の象徴であり、同時に彼が守りたい理想の色でもある。
におは、未来の読者の心を代弁するキャラクターなんだ。
◆土方歳三
冷静沈着な戦略家であり、同時に壬生浪士組の「影の心臓」。
感情よりも結果を重視し、「誠」の文字に己を縛る。
彼の正義は、におのそれとは正反対。
だが、その生き方はにおにとって最大の道標となる。
南条的に言えば、「冷酷の中に優しさを隠してるタイプ」。
そのギャップがとにかく痺れる。
◆近藤勇
理想主義者であり、純粋な“光”の側に立つ男。
だが、彼もまた組織を守るために汚れ仕事を背負う。
『青のミブロ』の近藤は、史実よりも人間臭く描かれていて、理想を掲げるリーダーの限界を象徴している。
におが理想を信じるのは、近藤の光に惹かれているからだ。
◆芹沢鴨
暴君であり、同時に最も“自由な男”。
彼の存在は壬生浪士組という組織の歪みを可視化する役割を果たす。
狂気的な暴力と、時折見せる人間的な優しさのギャップが恐ろしく魅力的。
俺は正直、芹沢の破滅を見た時、少し泣いた。
なぜなら彼は、誰よりも“理想に殺された男”だからだ。
◆沖田総司
若き天才剣士。
明るく飄々としながらも、どこか死の影を背負っている。
におに対しては兄のような優しさを見せ、彼に“青を澄ませる方法”を教える存在。
沖田の「青」の捉え方は、作品後半のメッセージそのものに直結している。
◆田中太郎
作中屈指の伏線キャラ。
芹沢に拾われた過去を持ち、のちに暗殺編でその因縁が爆発する。
彼の「正義」は復讐と忠義の狭間にあり、におとの対比で“もう一つの青”を体現している。
こうして見ると、『青のミブロ』という作品は「正義のモザイク」なんだ。
誰もが正義を掲げ、誰もが誰かを斬る理由を持っている。
それぞれの信念がぶつかり合って、血と涙と誠が交わる。
俺はここに、この作品の真の強さを感じる。
史実に縛られない自由さ、現代的な問いの鋭さ、キャラの人間臭さ。
全部が混ざり合って、結果として“青のミブロ”という奇跡のバランスが生まれている。
まるで、幕末に生きる少年たちの魂が現代に転生して、もう一度「何が正しいのか」を語っているような感覚になる。
第1部前半:におが見た“正義”の始まり
『青のミブロ』の第1部前半は、まさに「正義とは何か」というテーマの種が撒かれるフェーズだ。
ここで描かれるのは、少年・におが「理想」と「現実」の落差に心を引き裂かれていく過程。
この章を読むと、彼がどれほど純粋で、どれほど無力で、そしてどれほど“正義に飢えていた”かが痛いほどわかる。
俺が初めてこの章を読んだとき、まるで深夜に自分の過去を突きつけられたような気分になった。
「信じたいのに、世界が信じさせてくれない」──それがにおの出発点だ。
路地裏の少年、にお──正義を知らない純粋さ
物語の冒頭、におは京都の路地裏で生きている。
親を失い、貧しさと暴力の中で、ただ“生き延びること”しかできない少年。
だが彼は、そんな中でも「誰かのために動きたい」と思ってしまう。
それが彼の呪いであり、同時に才能でもあった。
ある夜、におはある浪士を助けたことで、土方歳三と出会う。
その瞬間、彼の人生は変わる。
土方の放つ空気は、まるで現実そのものだった。
無駄な言葉を一切使わず、におの理想を一瞬で粉砕する。
「正義なんざ、勝った奴の名前がそう呼ばれるんだ」。
この台詞は、『青のミブロ』という作品のテーマを象徴する“第一の刃”だ。
におはショックを受けながらも、土方に惹かれる。
なぜなら、彼の中に“恐ろしく誠実な冷たさ”を感じ取ったからだ。
土方は優しくない。
だが、彼ほど人の生き様に真摯な男もいない。
その矛盾がにおを掴んで離さない。
俺が思うに、この冒頭の出会いはただの「師弟の始まり」ではない。
これは、におが“現実を愛する練習”を始めた瞬間だ。
理想だけで生きられない時代に、自分の青を濁らせないために戦う。
その矛盾こそが、この物語の核にある。
壬生浪士組に入隊──「正義」を試される日々
におは土方たちの誘いを受け、壬生浪士組に入隊する。
最初はただの下っ端で、任務は掃除や雑用。
だが、におにとってそれすらも「生きる意味」になっていく。
彼は初めて、“誰かの役に立つ”という実感を得る。
その喜びが、彼をどんどん“青く”染めていく。
しかし同時に、組の中には“汚れた現実”もあった。
内部の争い、私刑、裏切り。
理想と現実の温度差が、におを徐々に追い詰めていく。
それでも彼は逃げない。
「俺は俺の信じた正義を、ここで探す」と心に決める。
この頃から、におは土方に強く影響を受け始める。
戦場で恐怖を抑えきれず震えるにおに、土方は言う。
「怖えなら、それを知っとけ。知らねえ奴が一番弱えんだ」。
この言葉で、におは少しずつ「強さ=恐れを知ること」だと理解していく。
俺はここで完全に心を掴まれた。
“強さの定義”を語る作品は多いが、『青のミブロ』は“恐れの定義”から始まる。
少年が「怖い」と言えること。
それを否定せず、「それでいい」と背中を押してくれる大人がいること。
この作品は、暴力と血の物語であると同時に、“成長と赦し”の物語でもあるんだ。
におの剣は、まだ未熟だ。
だが、その心の中には、誰よりも強い青が宿っている。
それは、汚れた時代にあってなお、澄み渡ろうとする“正義の初期衝動”。
第1部前半は、その青が最初に光を放つ瞬間を描いた、美しくも残酷な序章なんだ。
──そしてここから、におの「信念の色」は試されていく。
次の章、「血の立志団編」でその青は、血に染まりながらも輝きを失わない強さを見せることになる。
中盤:血の立志団編──理想と狂気の対決
『青のミブロ』第1部中盤、「血の立志団」編は物語全体のターニングポイントだ。
ここでは、におの正義が初めて真正面から“狂気”とぶつかる。
これまでのにおは、自分の中の信念を磨く段階にいた。
だがこの章では、それが「誰かの正義によって否定される」経験をする。
この章のテーマはずばり──「正義とは、人を救うためにあるのか、それとも選ぶためにあるのか」。
そしてそれを象徴する存在こそ、敵対組織「血の立志団」だ。
血の立志団──正義を狂気で塗り替える者たち
血の立志団は、幕府の腐敗を糾弾するために結成された暗殺集団。
彼らは「世を正す」という大義を掲げながら、要人の暗殺や情報操作を行う。
一見、彼らもまた「正義」を信じている。
しかしその正義は、におの信じる“人を救うための正義”とは決定的に異なる。
リーダーの直純(なおずみ)は、恐ろしいまでに理知的で、美しい理想主義者だ。
彼の言葉には一切の迷いがない。
「正義とは、誰かが傷つく覚悟の上に成り立つものだ」。
その信念は冷たく鋭く、だがどこか説得力がある。
におが持つ「守るための正義」は、直純の前では“子どもの理想”にしか見えない。
この構図がたまらない。
理想と理想のぶつかり合い。
どちらが間違っているとも言えない。
直純もまた、自分なりに“誰かを救いたい”と思っているのだ。
だが、その方法が血に染まっている。
におが戦うのは、悪ではなく「別の正義」なんだ。
この構成こそが、『青のミブロ』が他の歴史作品とは一線を画している理由だと思う。
俺の中ではこの章、ほとんど哲学書みたいな感覚だった。
正義を掲げる者が増えれば増えるほど、世界は壊れていく。
その皮肉を、血と涙で描く作者の筆が本気すぎて、ページをめくる手が止まらなかった。
におと直純の対決──理想のぶつかり合いが生んだ答え
におと直純の直接対決は、作品の中でも最も衝撃的な戦いの一つだ。
互いに「正義のため」に剣を振るうが、その先にあるものは破壊と絶望だった。
直純は言う。「人はいつか、血を流さなきゃ正義を知れない」。
におは叫ぶ。「そんなの、俺の信じたい正義じゃない!」。
この瞬間、におは初めて自分の正義を“他者と比べる”ことで、自分の芯を知る。
彼は理想を壊されながらも、それでも信じることをやめない。
結果として、におは重傷を負い、死の淵を彷徨う。
その姿は痛々しいほど美しい。
まるで、青が血に染まりながらも消えないように。
俺が特に震えたのは、におが意識を失う直前に見た“幻”の描写だ。
真っ青な空の下で、かつての自分が笑っている。
「正義なんて、知らなくていいよ」と言う幼い自分に、におは小さく答える。
「でも、俺は知りたい。たとえ傷ついても」。
──このやりとりで、俺は完全に涙腺崩壊した。
この章の最大の凄みは、“理想を信じ続けること”がどれほど痛みを伴うかを徹底的に描いたことだ。
におは理想に殴られ、現実に踏みつけられながらも立ち上がる。
そして、その痛みこそが彼を“本物の青”に変えていく。
南条的に言えば、この章は“正義が思春期を卒業する瞬間”だ。
誰かに信じてもらう正義ではなく、「自分が信じたいから信じる正義」へ。
におはこの戦いで、初めて「自分の青」を他人に奪われない強さを手に入れる。
それが、この後の芹沢暗殺編につながる伏線でもある。
この血の立志団編を読むと、単に幕末の剣劇漫画ではなく、“現代社会の寓話”として読むことができる。
SNSでの正義、集団の中での理想、孤立する個の痛み。
その全部を、におと直純の剣が象徴している。
この作品、マジで深すぎる。
──そして、におが重傷から立ち上がる頃。
物語は最大の運命を迎える。
“正義の組織”が自らの正義によって血に染まる瞬間、
芹沢鴨暗殺編が幕を開けるのだ。
クライマックス:芹沢鴨暗殺編

ここから『青のミブロ』は、まさに「正義の墓場」へと突入する。
第1部最大の山場──芹沢鴨暗殺編。
これまで、におは“外の敵”と戦ってきた。
だが、ここでは“内なる正義”が仲間同士を引き裂いていく。
正義を掲げた組織が、自らの理想によって崩壊していく過程を、これほどまで鮮烈に描いた少年漫画が他にあるだろうか。
作者・安田剛士はこの章で完全にギアを上げ、史実を越えて“信念の殺し合い”を描いている。
暗殺の予兆──新見錦の切腹と内部崩壊の始まり
物語は、新見錦の切腹から動き出す。
芹沢派と近藤派の対立が激化する中、内部粛清の第一波として新見が犠牲になる。
この出来事が、壬生浪士組を完全に二分した。
“正義のための犠牲”が、いつしか“保身のための犠牲”に変わっていく。
芹沢は粗暴で独断的だが、決してただの悪ではない。
彼は「武士たる者の誇り」を誰よりも信じていた。
だが、その信念が暴力という形で噴出し、次第に組織の足枷となっていく。
彼の酒乱、癇癪、暴走は全て“理想が壊れていく音”に見える。
対して、土方と近藤は“組織を守るための正義”を選ぶ。
つまり、ここでは正義が二つに割れている。
芹沢の正義=信念の純粋さ。
土方の正義=理想を守るための現実的な決断。
そのどちらも間違っていないのが、この章の地獄みたいな面白さだ。
俺は正直、この「正義の分裂」を描く構成に鳥肌が立った。
敵がいないのに血が流れる。
勝利がないのに戦いがある。
ここから『青のミブロ』は、歴史漫画の皮を脱ぎ捨て、“魂の戦争記”に進化する。
八木邸の夜──誠を賭けた刃が交わる瞬間
そして訪れる、雨の夜。
舞台は八木邸。
歴史上でも語り継がれる“芹沢暗殺事件”がここで再現される。
だが、安田版ではそこに“におの視点”が加わることで、史実とはまるで違う感情線が生まれる。
におはその夜、偶然にも八木邸へと駆けつける。
しかし、目にしたのはすでに刃が交錯する修羅の光景だった。
芹沢は酒に酔いながらも、最後まで笑っていた。
「……てめぇら、覚悟はできてんだろうな」。
その言葉に、土方は静かに答える。
「誰が正しいかなんて、今はどうでもいい。──これが俺たちの答えだ」。
この一連の描写は、漫画的演出を超えて“死の儀式”に近い。
芹沢は逃げず、戦い、誇りを持って散る。
彼の最期の瞬間、コマ全体が白く染まる。
まるで彼の“青”が完全に消え、空へ還っていくかのようだ。
におはただその光景を見ていることしかできない。
剣を抜けない。
叫べない。
ただ震えながら、芹沢の亡骸を前に涙を流す。
この描写が本当に痛い。
におはまだ少年で、彼にとって芹沢は「理想を見せてくれた大人」だった。
だが、その大人を殺したのもまた“正義”だった。
俺はこの場面を読んで、正直しばらくページを閉じた。
「正義って、誰のためにあるんだ?」という問いが、頭から離れなかった。
土方の決断は間違っていない。
だが、におの涙もまた正しい。
『青のミブロ』はここで、“勝者も敗者もいない正義”を提示してくる。
それがあまりに人間的で、あまりに苦しい。
南条的に言えば、この章は「理想の死」であり「現実の誕生」だ。
少年が夢を殺す瞬間、大人になる。
におにとって、芹沢鴨は“理想の象徴”だった。
その象徴を斬り捨てる世界の中で、彼はもう一度青を選び直す。
それが、この物語の核心だと思う。
この暗殺編を読むとき、読者はみんなにおになる。
剣を握ることもできず、ただ目の前で理想が崩れていくのを見つめるしかない。
それでもなお、彼は立ち上がる。
なぜなら、彼の中にはまだ“澄んだ青”が残っているからだ。
──そして、芹沢の死を境に。
ミブロは“新選組”へと姿を変える。
血に染まった青は、誠の旗へと変わる。
だが、におの瞳の奥にはまだ迷いが宿っていた。
その迷いこそが、次章「におの正体と『青』の意味」へとつながっていく。
におの正体と「青」の意味
芹沢鴨の死を経て、壬生浪士組は「新選組」へと変わっていく。
だがその中で、唯一“青”を失わなかったのが、主人公・におだった。
彼は仲間の血を見て、理想の崩壊を見て、それでも剣を手放さなかった。
なぜなら、におという存在自体が──「誠」と「理想」の狭間に生まれた象徴だからだ。
この章では、におというキャラクターの正体、そしてタイトルにもなっている“青”の真意を解き明かす。
俺に言わせれば、この章を理解しないと『青のミブロ』は半分も読めていない。
におという存在──「史実にいない少年」が背負った宿命
まず最初に押さえておきたいのは、におが史実上には存在しないキャラクターだということ。
実在の人物たちに囲まれながら、彼だけが“虚構”として立っている。
この構造がとてつもなく巧い。
史実のリアリティの中で、におは読者の代弁者であり、時代の魂そのものだ。
作中で彼の出自は明かされていない。
ただ、彼が「青い瞳」を持ち、「白髪」に近い髪をしているという描写には象徴的な意味がある。
血にまみれた時代の中で、彼だけが“染まりきらない色”を持つ。
それが、彼の“正義の純度”を可視化している。
ある読者考察では、「におは亡き者たちの願いの集合体」ではないかとも言われている。
彼の行動には、死者の後悔を晴らすような一途さがある。
ただし、作品内では一切明言されない。
作者・安田剛士は意図的に“語らない”。
それは、におの正体よりも「彼が何を信じるか」が重要だからだ。
俺が思うに、におというキャラクターは「信念のリトマス試験紙」なんだ。
彼に触れたキャラは皆、自分の中の正義の色を見せられる。
芹沢は赤、土方は黒、近藤は白、そしてにおは青。
この四色が混ざり合って、作品全体の情緒と倫理観を作り上げている。
つまり、におは物語の中心でありながら、“答えを出さない存在”なんだ。
それが最高に文学的で美しい。
「青」という色が象徴するもの──純粋・痛み・そして覚悟
“青”という色は、物語の根幹テーマを担っている。
この作品の青は、青春や希望の象徴ではない。
むしろその逆で、「痛みの中でも信念を手放さない人間の色」だ。
芹沢が赤(土と血)を象徴するなら、におの青は空。
赤と青が交わると、紫──すなわち“死”と“再生”の色になる。
つまり、芹沢の死を経て、におはその青をより深く、より静かな色へと変化させたんだ。
また、沖田総司とのやり取りも印象的だ。
「青ってさ、混じると何にでも染まる。でも、澄ませば芯が見える」。
この言葉は、『青のミブロ』という作品全体の哲学そのもの。
におは混ざり、傷つき、濁っても、それでも澄ませようとする。
その姿勢こそが、真の“誠”だと俺は思う。
この“青”は、現代社会にも響くテーマだ。
SNSや社会の同調圧力に染まりながらも、「自分の芯を澄ませよう」とする若者の物語として読むと、異様にリアルなんだ。
におが見せる迷いも、怒りも、泣き顔も全部、今を生きる俺たちの写し鏡だ。
俺はこの章を読むたびに、自分の中の青を確認する。
どれだけ疲れて、どれだけ濁っても、それでもまだ“好きなもの”や“信じたいこと”がある限り、俺たちは生きていける。
におはその象徴だ。
彼は、「信じることの痛み」を知りながらも、信じることをやめない。
──その姿こそ、この作品が放つ最も強い光だ。
そして、におの青はまだ完成していない。
芹沢を斬った世界の中で、彼がどんな色に染まるのか。
その答えは、第二部へと託されている。
『青のミブロ』はまだ終わっていない。
におの青も、俺たちの青も、まだ澄みきっていないのだ。
第一部完結:それぞれの“青”が選んだ道

芹沢鴨の血が乾いたあと、壬生浪士組は正式に「新選組」となる。
だが、組織が新しい名を得た瞬間、そこにいた男たちは確実に何かを失った。
理想。友情。誇り。そして“青”──それぞれが抱いていた純粋さだ。
第一部のラストは、まるで夜明けのような静けさで終わる。
だが、その静けさの中には、確かに燃え尽きた“青の残響”がある。
『青のミブロ』という作品は、ここで一つの物語を閉じる。
だが同時に、第二部に向けた「もう一つの青」の始まりでもある。
俺はこのラストを読んで、「終わった」というよりも、「息を呑んで待たされている」感覚になった。
なぜなら、ここで描かれたのは“結末”ではなく、“覚悟の始まり”だからだ。
芹沢の死が残したもの──誠の再定義
芹沢の死は、ミブロの内部に残酷な浄化をもたらした。
それは、腐敗を断ち切るための犠牲であり、同時に“誠”の再定義でもあった。
土方と近藤は、芹沢を斬ることで組織を守った。
だが、彼らの眼には迷いがあった。
芹沢を殺したのは、自分たちのためか、正義のためか──その答えは誰にも分からない。
におは、そのすべてを見ていた。
彼は芹沢の死体の前で泣き崩れた少年から、再び立ち上がる。
剣を握る手は震えていたが、その目は確かに澄んでいた。
「俺は、この青を濁らせたくない」──そう心の中で誓うにお。
この言葉こそ、作品タイトルの真の意味を象徴している。
芹沢という破滅のカリスマが消えた後、残された者たちはそれぞれの“青”を持って生きる。
土方は冷たい青。
近藤は希望の青。
沖田は儚い青。
そして、におは澄んだ青。
その色が混ざり合って、新選組という名の“新しい誠”を生み出した。
俺はここで気づいた。
『青のミブロ』というタイトルは、ただの象徴じゃない。
それはこの組織そのものを指している。
まだ誠に染まりきらない、若く不完全な時代の名だ。
つまり、“青のミブロ”とは、誠になる前の魂たちの物語なのだ。
それぞれの道、そして第二部への布石
ラストシーン、におと沖田の会話は静かな余韻で物語を締めくくる。
「青ってさ、混じると何にでも染まる。でも、澄ませば芯が見える」。
沖田は笑いながらそう言い、空を見上げる。
におは黙ってその隣に立ち、同じ方向を見る。
この会話には、あらゆる矛盾を抱えた人間の希望が詰まっている。
におはまだ未熟だ。
だが、もう迷わない。
「誰かの正義に従うのではなく、自分の青を貫く」ことを選んだ。
その決意は、物語全体の答えであり、同時に次の物語への道しるべだ。
新選組としての未来には、池田屋事件、禁門の変、そして多くの死が待っている。
だが、その中でにおがどんな色を放つのか。
芹沢が残した「誠の呪い」をどう超えていくのか。
それが、第二部の核心になるはずだ。
南条的に言えば、第一部のラストは“希望の仮死状態”。
すべてが終わったようで、実はまだ何も始まっていない。
沈黙の中に、熱が残っている。
におの青が、次にどんな血を吸うのか。
その予感が、読者を狂おしく待たせる。
俺はこのラストを読み終えて、深夜に本を閉じたあと、しばらく動けなかった。
この物語の“青”は、決して眩しくない。
けれど、どこまでも優しい。
俺たちが何度でも立ち上がれるように、心の奥で小さく光り続ける。
──だからこそ、『青のミブロ』はまだ終わらない。
まとめ:『青のミブロ』は、正義と青春の“痛み”を描いた魂の物語
『青のミブロ』は、単なる幕末アクションでも、史実の再演でもない。
それは、「正義とは何か」「信念を貫くとはどういうことか」を徹底的に突き詰めた人間ドラマだ。
におという少年の成長物語を通じて、理想が現実に壊される痛みと、それでも信じる勇気を描き切っている。
芹沢鴨の死、土方と近藤の葛藤、そして“青”という色に込められた未熟さと覚悟。
それぞれのキャラクターが抱く「自分だけの正義」が交差し、ぶつかり、時に壊れながらも、確かに何かを残していく。
この作品の美しさは、“正義を貫いた者が勝者とは限らない”という現実の中に、確かな人間の温度を宿していることだ。
第一部では、“青”がまだ濁りきっていない未熟な信念として描かれた。
そして第二部では、その青が血や涙と混ざりながら、より深く、より静かな色へと変化していくはずだ。
におがどんな結末を迎えるのか──それは、俺たち読者一人ひとりが持つ「正義の色」に委ねられている。
南条的に言えば、『青のミブロ』は“正義の哲学書”であり、“青春の墓碑銘”でもある。
読んで熱くなり、泣いて、そしてまた立ち上がる。
その体験ができる漫画は、今の時代そう多くない。
俺がこの作品を推す理由はシンプルだ。
「信念を持って生きることは、こんなにも痛くて、こんなにも美しい」──その事実を、ページの隅々まで刻み込んでいるから。
『青のミブロ』は、血と青で描かれた“生きる証明”なんだ。
最後に──今読むべき理由
今この瞬間、『青のミブロ』を読むことには意味がある。
誰かの言葉が正義を上書きするこの時代に、におの“青”は強烈なメッセージを放つ。
「誰かに染められるくらいなら、俺は俺の青でいたい」。
この一言が、あなたの胸にも刺さるはずだ。
そして、2025年12月からはアニメ第2期「芹沢暗殺編」が放送開始。
漫画で描かれた“正義の崩壊”が、アニメーションとしてどんな息づかいを見せるのか──見逃せない。
まだ『青のミブロ』を読んでいない人へ。
この作品は、ただの歴史漫画じゃない。
それは、あなた自身の“信じる力”を取り戻す物語だ。
──“青の誠”は、まだ終わらない。
FAQ:『青のミブロ』をもっと深く知るために
Q1. 『青のミブロ』は史実に忠実?
A. 基本的な史実(壬生浪士組の結成や芹沢鴨の暗殺など)には沿っているが、作品独自の演出・キャラ心理が強く描かれている。
実在の人物を「象徴」として再構築しており、史実再現よりも“信念と正義の物語”としての完成度を優先している。
特に、芹沢の最期が「酔って討たれる」ではなく「誇りを持って迎え撃つ」演出になっているのは、安田剛士の哲学的改変だ。
Q2. におの正体は明かされる?
A. 現時点(第13巻時点)では、におの出生や正体は明かされていない。
ただ、彼の容姿や行動には明確な“象徴性”がある。
青い瞳=理想。白髪=純粋な魂。
作中で彼は「血に染まりながらも青を失わない」存在として描かれ、“正義を貫く人間の化身”とも言える。
今後の第二部で、その意味が掘り下げられる可能性が高い。
Q3. 第二部はいつ始まる?内容は?
A. 作者・安田剛士は、第一部完結時のコメントで「この続きも描くつもり」と明言している。
物語的には、次の舞台が「池田屋事件」へと繋がる可能性が濃厚。
におの精神的成長、土方の覚悟、そして“青の終焉”が描かれると予想される。
おそらく次は「誠になる前の、最後の青」がテーマになるだろう。
Q4. アニメ化や実写化の予定はある?
A. はい、正式に **第2期アニメ「芹沢暗殺編」** の放送が決定している。
放送開始日は **2025年12月20日(土)夕方5時30分** で、読売テレビ・日本テレビ系で全国ネットにて放映予定。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
アニメ化はすでに第1期(2024年10月~2025年3月まで)も成功を収め、制作体制・スタッフ・演出力すべて評価が高かった。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
現時点では実写化の発表はないが、アニメ2期が動き出すことで、将来的なメディア展開が期待されている。
Q5. 『青のミブロ』が他の新選組作品と違う理由は?
A. 一言で言えば、“信念の対話”を描いているから。
多くの新選組作品は「忠義」や「滅びの美学」が中心だが、
『青のミブロ』は「正義とは何か」を時代や立場を超えて問い直す。
だからこそ、現代の読者にも刺さる。
におの青は、幕末ではなく今を生きる俺たちの心の色なんだ。
情報ソース・参考記事一覧
- Renote|『青のミブロ』ネタバレ解説・考察まとめ
― 登場人物整理と物語前半の構成理解に最適。におの思想形成の流れを丁寧に解説。 - Ani-Merit|芹沢鴨の最期シーン徹底分析
― 暗殺の経緯、土方の決断、史実との比較を細かく整理。 - note|第13巻レビュー「芹沢が託した願いと呪い」
― 第一部完結の意図、キャラクター心理の変化を深く考察。 - 時代電気|壬生浪士組の崩壊と芹沢劇場の始まり
― 組織内部の動きと新見錦の切腹事件の詳細が読める。 - Ani-Merit|におの正体と「青」の意味考察
― オリジナルキャラとしての立ち位置と“青”の象徴性を詳しく分析。 - ciatr.jp|血の立志団編まとめ
― 直純との対決、理想と狂気の衝突を整理。作品の思想的中心を解説。 - Manga Navi|『青のミブロ』における誠と裏切り
― 芹沢暗殺シーンの演出分析と“誠”という概念の再定義を論じる。
※上記リンクはすべて外部情報をもとに独自整理した考察用参考資料です。
記載内容の権利は各運営者・著者に帰属します。
記事内の引用・要約は読者理解を目的としたものであり、商用利用は行っておりません。

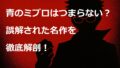

コメント