あの伝説の怪盗三姉妹が、令和の街に帰ってきた。
――そう聞いた瞬間、胸がざわついた人は多いはずだ。
40年ぶりに蘇った『キャッツ♥アイ』。
だが、ただのリメイクだと思って観ると痛い目を見る。
声も、絵も、テンポも、思想までも、すべてが変わっていた。
この記事では、3話までを踏まえて“旧作と違う5つの衝撃”を徹底解剖する。
懐かしさだけで語れない、この作品の「令和的進化」を、オタク評論家・南条蓮が全力で語る。
──時代を越えて、キャッツ♥アイは今も俺たちの心を盗みに来る。
声優交代と演技の“ズレと接点”
旧作『キャッツ♥アイ』の記憶を持つ世代にとって、最初の衝撃は間違いなく「声」だ。
あの頃、1983年の深夜、ブラウン管の向こうから響いた戸田恵子・藤田淑子・坂本千夏――この三人の声が、まさに〈キャッツ〉そのものだった。
彼女たちの演技には、当時の“都会の艶”と“少女の夢”が同居していた。
大人びた女の色気と、若い恋の青さ。そのギリギリのバランスを声で保っていた。
だから令和版でキャストが変わると聞いた瞬間、俺の脳裏に浮かんだのは「そのバランスをどう再構築する気なんだ?」という半分の不安と半分の好奇心だった。
3話まで観終えて、俺は確信した。
これは“リメイク”ではなく、“継承”だ。声が変わっても、魂は確かに受け継がれている。
旧作の「記憶の声」が持つ魔力
旧作の声優陣は、まさに80年代アニメ黄金期の中心を担った世代だった。
来生瞳=戸田恵子の声は、明るさと芯の強さを両立していた。
彼女の「俊夫、あなたって本当にバカね」という台詞には、恋愛と職業、愛と秘密を同時に抱える女の複雑さがにじんでいた。
泪=藤田淑子の声は、まるで夜風のように静かで、しかしどこか危険な香りをまとっていた。
そして愛=坂本千夏の声は、三姉妹の中で唯一“陽”のエネルギーを放ち、作品の重さを軽やかに中和してくれた。
この三人の声の重なりは、80年代独特のアナログなマイク録音の“空気感”と相まって、まるで一枚の音楽のようだった。
あの息遣い、あの間の取り方――それこそが『キャッツ♥アイ』の「リズム」だったんだ。
だから、俺たち旧作ファンの脳は“音の記憶”でキャラを識別している。
声が違うと、無意識に「別の人だ」と判断してしまう。
令和版が最初に直面したのは、その“記憶との戦い”だと思う。
でもな、よく聴くと、令和版のキャストたちはその「音の記憶」を踏まえた上で、あえて別のリズムを選んでいる。
旧作のテンポを真似しない。
むしろ現代的な“間”や“沈黙”で新しい緊張感を作っている。
つまり、“同じ楽譜”を違う楽器で演奏しているようなものなんだ。
令和版の「静」と「間」で語る演技革命
小松未可子(瞳)、小清水亜美(泪)、花守ゆみり(愛)。
この3人は、いずれも令和アニメの第一線で「感情の間をコントロールできる声優」たちだ。
彼女たちの演技は、80年代のような“セリフで説明する演技”ではなく、“沈黙で語る演技”にシフトしている。
特に第2話の屋上シーン。
泪が「これは、まだ言えない」と小さくつぶやく瞬間。
小清水の声は、まるで息を止めたように細く、冷たい。
その静寂の中に「泪」という人物の過去と決意が一瞬で立ち上がる。
旧作の藤田淑子版が“包み込むような静けさ”だったのに対し、小清水版は“張り詰めた緊張”で泪を描いている。
どちらも正解。時代の文法が違うだけだ。
小松未可子の瞳も面白い。
旧作では瞳=リーダーでありヒロイン、つまり“中心に立つ存在”として描かれていた。
しかし令和版の瞳は“揺れるリーダー”だ。
彼女の「正義」と「家族愛」の間での葛藤を、小松は声のトーンで丁寧に表現している。
第3話の「私たちのやり方で」という一言――あれは、旧作の瞳なら明るく言い切っただろう。
だが今の瞳は、少しの逡巡と呼吸のズレを残して発している。
その“間”こそが、令和の現実感なんだ。
そして花守ゆみりの愛。
これは正直、俺の中で“最も令和らしいキャラ造形”だと思う。
愛は旧作ではコミカルなムードメーカーだったが、新作では少し大人びた“共犯者的ポジション”に近い。
花守の声は軽やかだけど、その裏に冷静な判断力がある。
軽い言葉の中に深さを仕込む、これが令和の“キャラのリアリティ”なんだ。
三姉妹の呼吸が揃う瞬間──チームとしての“声の演出”
第3話の終盤、三姉妹がミッションを遂行する場面。
このシーンで俺はハッとした。
声のテンポ、息継ぎ、掛け合いのリズムが完璧に揃っていたんだ。
まるで一つの呼吸で動いているような“チームのリズム”。
旧作は、三姉妹の個性を際立たせるためにあえてテンポをずらしていた。
瞳が早口で、泪がゆっくり、愛がリズミカルに。
その“ズレ”が人間らしさだった。
だが令和版は真逆の設計だ。
三人の声を「一つのグルーヴ」にまとめ上げている。
これがリメイク版最大の“音響的進化”だと思う。
その裏には、確実に音響監督の計算がある。
最近のアニメは、録音時に全員が別撮りすることが多い。
にもかかわらず、ここまで呼吸が合っているのは、“編集で意図的に間を合わせている”ということだ。
つまり、『キャッツ♥アイ』はもう一度“音楽的作品”に戻ってきた。
俺は思う。
声優交代というのは、単なる人の入れ替えじゃない。
それは「演技の時代性」を更新する儀式なんだ。
80年代の“情緒の声”から、令和の“内省の声”へ。
感情のアウトプットではなく、感情の構造そのものを表現する。
だからこそ、違う声でも“同じキャッツ♥アイ”を感じられる。
それは単なる懐古ではなく、進化だ。
この演技の呼吸の変化を感じ取れた瞬間、俺は少し泣きそうになった。
作画タッチの変化──光、影、線の“質感”
旧作『キャッツ♥アイ』の映像を久々に見返すと、あの「手描きの温度」に胸がギュッとなる。
線は太くて柔らかく、色は少し滲むように広がる。
アナログの筆跡がそのままキャラの呼吸になっていた。
そして夜景はどこか霞んでいて、まるで80年代の東京の湿度そのものを閉じ込めたようだった。
一方、令和版はまったく別のアプローチを取っている。
“美麗”“シャープ”“シネマライク”――この三拍子を揃えた映像。
制作はライデンフィルム。
『ベルセルク』や『アルスラーン戦記』で培ったリアル寄りの作画を基盤に、アナログ線の余韻をデジタルで再構築している。
だが、ここで重要なのは「単に綺麗になった」ではなく、「質感の意味が変わった」ということ。
旧作の線は“愛嬌”のための線だったが、令和版の線は“現実感”のための線だ。
光と影のコントラストが強く、表情は立体的に描かれる。
それによって、キャッツ♥アイの三姉妹は“アニメキャラ”から“現代の女性”へと進化した。
俺はその瞬間、「ああ、令和のアニメはもう“美少女”を描く時代じゃない、“人間”を描く時代なんだ」と痛感した。
旧作の「夜のブルー」とアナログの余白
旧作の魅力は何よりも“夜の色”にあった。
背景に使われる群青のグラデーション、月光が反射するビルの窓、そして瞳の髪に宿る銀のハイライト。
どれもデジタルでは再現できない“アナログのムラ”が生んだ偶然の美だった。
1983年当時の東京ムービー新社は、セル画の重ね塗りや撮影処理で「夜の奥行き」を表現するのが得意だった。
つまり“暗闇の中の温度”を描けるスタジオだったんだ。
そのおかげで、キャッツ♥アイは単なる怪盗モノではなく、“光と影の中で生きる女たち”の物語として成立していた。
特に印象的なのが、旧作第3話の屋上シーン。
月明かりに照らされる三姉妹のシルエットが、淡いブルーで縁取られていた。
その“青の静寂”が、まるで彼女たちの孤独を代弁していた。
作画というより“絵画”。それが80年代の『キャッツ♥アイ』だった。
俺は思う。
あの時代の「粗さ」は、“人間の手で作られた物語”の証だった。
今のアニメがいくら高解像度でも、この“ノイズの温かさ”は再現できない。
だが、それを超える方法を、令和版は別の方向で掴もうとしている。
令和版が描く“影の密度”と質感の進化
令和版の作画は、一言で言えば「光と影の物理化」だ。
キャラの肌に当たる光はやわらかく、背景の陰影は緻密。
街灯、ネオン、窓の反射、車のヘッドライト――すべてが“存在感”を持って描かれている。
とくに第1話のアクションシーン、夜の美術館を滑走する瞳のカット。
カメラが横パンしながら追うその動きの中で、影がリアルに揺れる。
これこそデジタル作画の真骨頂だ。
だが、令和版は単なるCG的リアリズムでは終わっていない。
重要なのは、影の「感情表現」への転化だ。
旧作では“雰囲気”のために影を置いていたが、令和版は“心理”のために影を置いている。
たとえば第2話。
泪が一人で絵画を見つめるシーン、彼女の顔に落ちる影は、まるで「過去」という名の牢獄を暗示している。
照明が動かないのに、影が感情に合わせて変化して見える。
これは明確に演出設計された“心理照明”だ。
さらに、線そのものも進化している。
旧作では太く丸いアウトラインが多かったのに対し、令和版は線の太さをシーンごとに変えている。
アクション時はシャープで細く、感情描写では太く柔らかい。
この「線のリズム」がキャラの心拍を視覚化しているんだ。
俺が感動したのは、第3話で泪が笑うシーン。
光が彼女の頬をなぞる瞬間、影の層が3段階に分かれてる。
単なるグラデーションじゃない、呼吸の深さだ。
こういう“見えない感情”を絵で描けるのは、令和版スタッフの力量の証拠だと思う。
「色気」を再定義する作画──露出から質感へ
旧作『キャッツ♥アイ』と言えば、やはり“レオタード姿のセクシーさ”が代名詞だった。
しかし令和版は、その“色気”の概念を根本から更新している。
新作では、露出ではなく“光の当て方”と“表情の陰影”で官能を描く。
たとえば瞳のボディスーツ。
露出は少ないのに、光の反射と素材感で“肌の温度”を感じさせる。
これは明確に“現代的フェティシズム”へのアプローチだ。
表現規制の影響もあるが、それ以上に「視覚の知性」を意識している。
観る側に“想像させる余白”を残す。これが大人のエロスだ。
俺の中で最も象徴的だったのは、瞳が鏡越しに自分を見るカット。
旧作なら、ここで腰のラインを強調したはず。
だが令和版は、鏡に映るのは「目」だけなんだ。
視線を交わす瞬間の緊張――それこそが今の時代の“キャッツ♥アイ的色気”。
観る者の想像を盗む、それが令和の怪盗術だ。
南条蓮の視点:この“冷たさ”こそ、令和の美学
正直に言おう。
最初は俺も「綺麗すぎる」「冷たい」と感じた。
でも、3話を見終えた今なら断言できる。
この“冷たさ”こそが令和のリアリティなんだ。
80年代は「温度」でキャラを愛した時代。
令和は「距離」でキャラを見つめる時代。
その差を如実に映しているのが、作画の“質感”の変化だ。
近すぎず、遠すぎず。光と影のコントラストで感情を測る。
つまり、令和版『キャッツ♥アイ』は“温かいアニメ”ではなく“冷たい美術”を選んだ。
でもその冷たさの中に、人間の孤独と絆を描く。
そこにこそ、現代のアニメが進化した証があると思う。
今の時代に「怪盗三姉妹」を蘇らせるなら、この温度差こそが最も誠実なリメイクなんだ。
テンポ構成と語り口の刷新
リメイク作品の真価は、“語りの速度”に出る。
旧作『キャッツ♥アイ』が放送されていた1983年当時、アニメのテンポは「1話完結」が基本だった。
30分枠の中で事件が起き、キャッツが盗みに挑み、俊夫が追いかける。
最後には少しの恋愛ドラマを挟み、EDテーマで幕を閉じる――そのルーチンが心地よかった。
だが、令和版はそこを大胆に変えてきた。
“完結しない物語”を選んだのだ。
この選択は、単なる時代のトレンドではない。
令和版は“キャッツ♥アイという構造そのもの”を語り直している。
3話まで観て思うのは、旧作が「物語のスピード」で観客を惹きつけていたのに対し、
令和版は「感情の流速」で観客を引き込んでいるということ。
つまり、アクションではなく〈間〉で緊張を生む。
それが今のアニメのリアルだ。
旧作のテンポ──“事件が中心”のシナリオ構造
旧作『キャッツ♥アイ』の1話は、だいたい15分で事件が発生し、10分で解決、5分で恋愛またはギャグ。
いわば「週刊連載型アニメ」だった。
各話が独立していて、どこから観ても理解できる。
それがテレビの前の子どもたちには優しかった。
脚本家・酒井あきよしらによるテンポ設計は、セリフのテンポが命。
俊夫の早口と瞳のツッコミで場をつなぎ、感情よりも“軽快さ”で物語を駆動させていた。
視聴者の感情移入を強く誘導せず、テンポでリズムを取る。
この“スナップの効いたテンポ”が旧作の特徴だった。
でも同時に、それは“深掘りできない”という欠点も抱えていた。
瞳がなぜ怪盗を続けるのか、泪の過去は何なのか、愛が姉たちをどう見ているのか――
それらは背景として描かれることはあっても、物語の核心にはならなかった。
80年代テレビの制約の中では、それが最も美しい形だったんだ。
俺はあの時代のテンポを否定しない。
むしろ好きだ。
だが、それをそのまま今やるのは難しい。
NetflixやDisney+で観る現代の視聴者は、“時間の密度”に敏感だからだ。
だから令和版は「テンポの静寂」を武器にしてきた。
令和版の構成──“間”で語る新しいリズム
令和版『キャッツ♥アイ』の第1話から第3話を通して感じるのは、「情報を出さない勇気」だ。
旧作なら説明していた部分を、今作はあえて省略している。
その“沈黙”が、ストーリーを支配している。
第1話では、キャッツ三姉妹がなぜ再び盗みに戻ったのか、明確に語られない。
第2話では、泪の表情に過去の影がよぎるが、それが何なのかは一切明かされない。
第3話でも、俊夫との関係は“曖昧な視線”でしか描かれない。
だが、その分だけ〈余白〉が生まれる。
観る者に考えさせる、補完させる。
この手法は、まさに令和アニメのトレンドである“ポスト説明的演出”の典型だ。
特に印象的なのが第2話終盤の会話。
瞳が「私たちのやり方でやる」と言い、泪が何も言わずに頷く。
音楽が止まり、3秒の無音。
この3秒が、旧作30分分の感情を語っている。
言葉を削り、沈黙で繋ぐ。
この“間の美学”こそ、令和版が旧作を超えようとしている最大の挑戦だと思う。
俺はこの演出を「沈黙のアクション」と呼びたい。
派手なアクションじゃない。
呼吸と間のリズムで緊張を生む。
それが今作の本当の“怪盗劇”だ。
テンポの再定義──“走る”から“溜める”へ
旧作は常に走っていた。
キャッツが走り、俊夫が追いかけ、サウンドが跳ねる。
視聴者はテンポに乗せられて「楽しい!」と感じる構造だった。
一方で令和版は、走らない。
止まる。考える。
感情を“溜めてから動く”という、リアルタイムの重さを選んだ。
この変化は、単に脚本の違いではない。
映像編集の思想そのものが違う。
旧作では1カット平均2〜3秒。
令和版では1カット平均5〜8秒。
つまり、視聴者に“観る時間”を与えている。
たとえば、泪が夜景を見下ろすカット。
カメラが動かず、ただ風の音だけが流れる。
旧作ならナレーションやBGMが入る場面だ。
しかし令和版は音を止めた。
この“静けさ”が、むしろドラマを熱くしている。
俺は3話まで観て、このテンポが最初こそ“遅い”と思ったが、今では“深い”に変わった。
それは「テンポ=速さ」ではなく「テンポ=密度」だと気づいたから。
令和のアニメが旧作の速さを模倣しなかったのは、時代に対する誠実さの証拠だ。
この静かなテンポが生むのは、ノスタルジーではなく“没入”だ。
画面の中でキャラが呼吸しているのを感じる。
それこそが、現代リメイクの最大の進化。
キャラクターが“生きている速度”で物語が進む。
それが、令和版『キャッツ♥アイ』の新しいリズムだ。
南条蓮の視点:このテンポは「再生」ではなく「再構築」
令和版『キャッツ♥アイ』のテンポは、旧作を懐かしむためのものじゃない。
むしろ、旧作の構造を解体し、ゼロから“語りの呼吸”を再構築している。
旧作の疾走感が“時代の勢い”を象徴していたとすれば、
令和版の静寂は“現代の迷い”を象徴している。
どちらも〈時代の女たち〉を描いている。
今の三姉妹は、ただの怪盗ではない。
時間の流れの中で“自分たちの正義”を問い直す存在だ。
だから、テンポを遅くしたのは必然だ。
彼女たちは「走る」のではなく、「立ち止まる勇気」を選んだんだ。
俺はこのテンポに、“成熟した物語”の香りを感じる。
旧作のファンほど、この静けさを楽しめるはず。
だって、俺たちももう大人になった。
だから、キャッツ♥アイもまた、静かに、深く、時間を盗むんだ。
原作回帰志向と改変点のバランス
リメイクという行為は、常に「原作への愛」と「時代への敬意」の綱引きだ。
旧作『キャッツ♥アイ』は、北条司の原作を下地にしつつも、テレビアニメとしての“娯楽性”を最優先に再構築された。
原作が持つ〈哀しみ〉や〈家族の物語〉の要素は削ぎ落とされ、明るく軽快なラブコメとして放送された。
つまり旧作は、原作の“現代的女たち”を“昭和のヒロインたち”として描き直した作品だった。
そして令和。
今度の『キャッツ♥アイ』は、その反動として「原作への回帰」を強く意識している。
だが、それは単純な再現ではない。
原作を“現代の倫理と視点”で再翻訳するという挑戦だ。
それがこのリメイクの核心であり、最大の賭けだと思う。
原作へのリスペクト──“北条司的世界”の再構築
まず注目したいのは、令和版が意図的に“北条司的ディテール”を復活させている点だ。
原作では、美術品を盗む動機が「父の行方を追うため」であり、単なる怪盗劇ではなかった。
旧作アニメではこの設定がぼかされ、家族ドラマの比重が薄かったが、令和版では再び中心に据えられている。
第1話で登場する絵画の署名「M.K.」は、まさに原作ファンならピンとくる“父の痕跡”のモチーフだ。
これを物語の軸に戻したことで、物語全体に“北条司らしい哀愁”が戻ってきた。
この選択は明確に原作回帰路線だ。
さらに、第3話で登場した“神谷真人”の存在も重要だ。
旧作には登場しなかったが、原作では冴羽獠(シティーハンター)の原型的存在として描かれたキャラ。
令和版で彼が登場したことは、単なるファンサービスではなく、北条ユニバースの再構築を意味している。
つまり、令和版『キャッツ♥アイ』は「リメイク」ではなく「北条司作品の再接続」なのだ。
俺はここに一番グッときた。
“懐かしさ”じゃなく、“物語の血脈”を取り戻した感じ。
昭和の映像では削ぎ落とされた“原作の陰”が、令和の光で照らされている。
まさに、北条司に対する静かなオマージュだ。
設定と演出の改変──時代を越えるための“必然的アップデート”
一方で、令和版は大胆に“時代の壁”を取り払っている。
旧作の舞台はバブル前夜の東京。電話ボックス、フィルムカメラ、紙の地図。
今となってはノスタルジーの塊だ。
しかし、令和版の舞台は完全に“今”の東京。
スマホ、監視カメラ、AIセキュリティ、SNSニュース――すべてが現代仕様に更新されている。
特に面白いのは、キャッツの“盗みの方法”が現代化していること。
旧作では物理的な潜入や変装が主流だったが、今作ではハッキングやデータ侵入も併用されている。
「怪盗」という職業のアップデート。
物理的侵入から、情報的侵入へ。
つまり“盗む対象”が〈モノ〉から〈真実〉へと変わったのだ。
この演出の変化は、社会の変化そのものを映している。
80年代は“金と名声”が価値だったが、令和の時代に盗まれるものは“記録と秘密”。
キャッツたちが奪うのは、データベースの中に埋もれた「過去」だ。
彼女たちは、時代の情報の渦に抗う存在になった。
そしてもう一つ、個人的に重要だと感じたのは「暴力の扱い」だ。
旧作ではコメディ的暴力――パンチや投げ飛ばしなどが多かった。
だが令和版は、暴力を“現実的な痛み”として描いている。
打撃音が重く、表情がリアルに歪む。
その分だけ“命の重さ”がある。
この変化も、令和という時代の倫理観を反映している。
俺は、こういうアップデートが好きだ。
“変えた”のではなく、“時代に適応させた”。
この誠実さこそ、リメイクの美学だと思う。
改変のリスク──ファン心理とのせめぎ合い
ただし、原作回帰と時代改変の両立は、常にファン心理との綱渡りだ。
旧作ファンの一部からは「瞳のキャラが変わりすぎ」「泪がクールすぎる」といった声もある。
SNSでは“原作再現派”と“旧作思い出派”の議論がすでに始まっている。
その背景には、“キャッツ♥アイとは何か”という根本的な定義の違いがある。
ある人にとっては“スタイリッシュな怪盗コメディ”、ある人にとっては“家族の絆の物語”。
令和版はその両方を内包しようとしているが、どちらにも振り切れない難しさがある。
しかし俺は思う。
これは「違う作品になった」んじゃない。
むしろ、“キャッツ♥アイというテーマ”を再検証しているんだ。
旧作が“夢の女たち”を描いたなら、令和版は“現実を生きる女たち”を描いている。
それは変化ではなく、進化。
時代が違えば、女のかっこよさも変わる。
そして、キャッツ♥アイはいつの時代も“最も時代的な女たち”なんだ。
俺はそのブレなさに惚れている。
南条蓮の視点:これは「懐古」ではなく「継承」
3話まで観て思う。
令和版『キャッツ♥アイ』は、原作を“再現”していない。
むしろ、“原作を継承して再生産している”。
北条司の物語哲学――「正義と罪の境界で生きる女」――を、現代社会の文脈に置き換えているのだ。
瞳たちは、もはや80年代のファンタジーではない。
現代の孤独と向き合うリアルな女性像として描かれている。
それを“原作回帰”という言葉で片付けてしまうのはもったいない。
令和版は、「懐古」ではなく「継承」。
原作の血を絶やさずに、時代に合わせて心臓を入れ替えた。
それが、このリメイクの本質だ。
旧作を愛していた俺としては、あの頃の輝きを思い出しつつ、今の冷たい夜の光の中で再び彼女たちに出会えることが、何よりの幸福だ。
“あの三姉妹”は、確かに令和の街を生きている。
そして今も、俺たちの心を盗んでいく。
3話までで感じた“5つの衝撃”──変わったのは声と絵とテンポだけじゃない
3話まで観て、令和版『キャッツ♥アイ』が旧作とどこまで違うのか──その答えは「すべて」だ。
声優、作画、テンポ、構成、主題へのアプローチ。
どれもが変わっている。
だが同時に、その“変化の中心”には、確かに旧作の魂が生きていた。
ここでは、俺・南条蓮が令和版を3話まで観て体感した“5つの衝撃”を整理して語ろう。
それは、単なる懐古でも批判でもない。
80年代の名作が、2025年の東京にどんな形で蘇ったのかを、リアルに感じた記録だ。
令和の“キャッツ”が何を盗んでいるのか、その本質に迫る。
衝撃①:声優の演技設計が“感情から構造”へと進化していた
まず最初の衝撃は、やはり声。
旧作の声優が「キャラの感情」をそのまま外へ出すタイプだったのに対し、
令和版の小松未可子・小清水亜美・花守ゆみりは、“感情の構造”を演じている。
たとえば、第2話で瞳が俊夫に「私たちは、ただの泥棒じゃない」と言うシーン。
旧作なら、ここで一気に感情を爆発させていた。
しかし令和版の小松は、一呼吸置いて、抑え気味に言葉を吐く。
その「間」がすべてを語っていた。
彼女の演技は、セリフの裏に“沈黙の重み”を置いている。
これが今のアニメの演技哲学だ。
泣くでも笑うでもなく、“感じさせる”。
声優が「言葉の余白」で勝負する時代になった。
この静けさの演技に、俺は鳥肌が立った。
もはや声優というより、演出家だ。
衝撃②:作画のテーマが“視覚美”から“心理の質感”へ
二つ目の衝撃は、映像の「質感の進化」だ。
旧作は“見た目の華やかさ”を重視していた。
だが令和版は、“心の揺らぎ”を視覚的に描いている。
第3話の、泪が夜の街を一人で歩くシーン。
街灯がチラつき、ガラス越しに映る彼女の表情が歪む。
その揺れが、彼女の心の不安をそのまま映している。
これは絵ではなく“感情のカメラワーク”だ。
光の当て方一つで、キャラの心理が変わる。
旧作が“女を美しく撮る”作品だったなら、令和版は“女を生きるように描く”作品だ。
美しさよりも、痛みのリアル。
それが新しい『キャッツ♥アイ』の顔だと思う。
衝撃③:テンポが“走る物語”から“呼吸する物語”へ変化
三つ目の衝撃は、テンポの刷新。
旧作が走り抜ける疾走感を魅力としていたのに対し、令和版は徹底して“止まる”。
特に第2話終盤、キャッツが逃走後に屋上で沈黙するカット。
セリフが一切ないのに、三人の呼吸音だけが聞こえる。
まるで観客の呼吸とシンクロしているような静けさだった。
この「間」の使い方が、圧倒的に令和的。
かつての“テンポ=スピード”という概念を完全に壊し、“テンポ=体感”に置き換えている。
リズムではなく、時間の質で魅せる。
この挑戦を支えているのは、演出と音響の精密な設計力だ。
今のアニメ界でも、この“静寂で魅せる勇気”を持つ作品は少ない。
『キャッツ♥アイ』はそれを堂々とやってのけた。
俺はこのテンポを“沈黙のアクション”と呼びたい。
衝撃④:主題の焦点が“恋と盗み”から“記憶と再生”へ
旧作のキャッツは「恋と仕事の両立」を描いていた。
瞳と俊夫のロマンス、三姉妹の絆。
しかし令和版は明らかに違う。
3話までで見えてくるテーマは、“記憶”と“再生”。
失われた過去をどう受け入れるか。
家族という呪縛をどう超えるか。
彼女たちが盗むのは、モノではなく「過去」だ。
第1話で盗み出した絵画が、父の手掛かりであるという設定も象徴的だ。
この方向性は、令和のアニメの“ポスト家族論”に繋がっている。
血よりも、共有した時間こそが家族。
令和版『キャッツ♥アイ』はそのテーマを、盗みという行為で体現している。
俺はそこに深いロマンを感じた。
恋愛よりも、「絆」を盗み返す物語。
この変化は、間違いなく“令和の視点”だ。
衝撃⑤:サウンドと音楽が“感情演出”から“演出装置”へ
そして最後の衝撃。
それは、音楽だ。
旧作の『CAT’S EYE』(杏里)の軽やかで都会的なテーマは、時代の象徴だった。
一方で、令和版の主題歌(Ado「Steal the Night」)は、完全に“物語の内側”に入り込む。
テンポは遅く、ベースが重い。
歌詞も“奪う”“逃げる”ではなく、“隠す”“忘れる”がモチーフになっている。
つまり音楽が“キャラの心情を説明する”のではなく、“作品の精神を代弁する”役割に変わっている。
これは演出全体の意識変化を象徴している。
BGMの入り方、沈黙の時間、効果音の配置すべてが映画的。
特に第3話の無音パートは圧巻だ。
「音を消す」勇気が、令和版を一段上の作品にしている。
旧作が“音で盛り上げる”作品だったなら、令和版は“音で止める”作品だ。
音楽が物語を引っ張るのではなく、物語が音を呼ぶ。
この逆転が、まさにリメイクの美学だと思う。
南条蓮の視点:この5つの衝撃は、“作品の再定義”だ
3話まで観た俺の結論はこうだ。
令和版『キャッツ♥アイ』は、旧作の延長線上にはいない。
それは“再現”ではなく、“再定義”だ。
声優の演技がキャラの内面を再定義し、作画が感情の構造を再定義し、テンポが時間の密度を再定義した。
令和版は、「キャッツ♥アイとは何か?」という問いそのものに挑戦している。
その挑戦が生む“違和感”こそ、この作品の面白さなんだ。
旧作ファンが感じる懐かしさ。
新規ファンが感じるスタイリッシュさ。
その中間にある“静かな衝撃”こそ、令和版の心臓部だ。
俺にとってこの作品は、80年代へのノスタルジーではなく、“今を生きる女たちの物語”として刺さっている。
3話まででここまで“再定義”してくるなら、今後が怖いほど楽しみだ。
この作品、まだ本気を出していない。
キャッツはまだ、俺たちの心を盗み尽くしていない。
まとめ──令和版『キャッツ♥アイ』が盗んだのは“記憶”と“現在”だった
3話までを見終えて、俺が最も強く感じたのは「令和版は、俺たちの“記憶”を盗みにきた」ということだ。
旧作をリアルタイムで観ていた世代の記憶、懐かしさ、安心感。
それらを一度全部盗み去り、新しい“現在の感情”をそこに置き換えていく。
そんな構造を持ったリメイクだ。
声、絵、テンポ、演出、テーマ。
すべてが「今、この時代に“キャッツ♥アイ”を再定義するにはどうすべきか」という問いの答えとして作られている。
令和版は、懐古に甘えるどころか、“過去を再び盗み出す”という大胆な行為を選んだ。
だからこの作品は、単なる復刻ではない。
“時代泥棒アニメ”だと俺は思っている。
旧作ファンにとって──「変わった」ではなく「進化した」
もし旧作を愛している人が令和版を観て「違う」と感じるなら、それは正しい。
でもその“違い”こそが、この作品の成功の証だ。
80年代のキャッツ♥アイは「自由な女性たちの象徴」だった。
だが2025年の彼女たちは、「傷を抱えたまま前に進む女性たち」だ。
強さの種類が違う。
令和の三姉妹は、無敵ではない。
だが、だからこそ強い。
旧作を知る人にこそ、この変化を受け止めてほしい。
俺たちが歳を取り、時代が変わっても、瞳たちはその速度で走ってくれる。
過去を懐かしむ作品じゃない。
過去を再び“生きる”ための作品だ。
新規ファンにとって──“大人の物語”としての入り口
令和版『キャッツ♥アイ』は、旧作を知らない世代にとっても十分に刺さる。
なぜなら今作は“アクション”よりも“心理”を描いているからだ。
ストーリーよりも「人間の揺れ」が軸になっている。
SNS世代の観客は、派手な映像よりも、静かな共感を求めている。
瞳の迷い、泪の沈黙、愛の微笑。
それぞれが小さな痛みを抱えて生きる姿に、現代的なリアリティがある。
それは、もう“アニメ”という枠を超えている。
今作は、80年代を知らなくても、“生きづらさを知る人”なら誰でも心を掴まれる物語だ。
俺が言いたいのはこれだ。
『キャッツ♥アイ』はもう“過去の名作”じゃない。
“今を映す鏡”になっている。
だから、新規ファンも遠慮する必要はない。
この作品は、時代を超えて誰かの「現在」を救う物語なんだ。
南条蓮の視点:令和版は“盗みの物語”ではなく“生き直しの物語”
結論から言おう。
令和版『キャッツ♥アイ』の本質は、“盗むこと”ではなく“取り戻すこと”だ。
盗みという行為の裏には、常に「失った何かを取り戻したい」という衝動がある。
それが父の記憶であり、姉妹の絆であり、かつての自分自身。
この作品は、そうした“再生”の物語として描かれている。
盗むことで、自分たちの心を取り戻していく。
その静かな痛みと、立ち上がる強さが、令和の『キャッツ♥アイ』を唯一無二にしている。
俺はこのリメイクを、ただの再放送の延長とは思っていない。
むしろ、アニメ史の中で「リメイクの成功例」として語られる未来が見える。
3話までの段階で、ここまで明確に「意志」を持った作品は少ない。
声優・演出・音響・脚本、すべてが一つの思想に向かって動いている。
それは、“時代における女性の再定義”というテーマだ。
だから俺はこう呼ぶ。
令和版『キャッツ♥アイ』は、“心を盗むリメイク”だ。
懐かしさで泣くんじゃない。
「今の自分」を見透かされて、泣く作品なんだ。
そして気づけば、また俺たちはキャッツに盗まれている。
青春を、憧れを、そして今この瞬間の心を。
──それでいい。だって、それが彼女たちの仕事だから。
FAQ(よくある質問)
Q1:令和版『キャッツ♥アイ』はどこで観られますか?
令和版『キャッツ♥アイ』は、Disney+(ディズニープラス)「スター」枠で独占配信中です。
2025年9月26日より全世界同時配信が開始され、毎週金曜に新エピソードが更新予定です。
詳細は公式サイト:Disney+公式『キャッツ♥アイ』ページをご確認ください。
Q2:令和版は旧作(1983〜85年版)の続編ですか?
続編ではなく、完全なリブート(再構築)版です。
北条司原作漫画をより原作寄りの構成で再解釈しており、旧作のストーリーや設定は引き継がれていません。
ただし、旧作ファンが楽しめる“オマージュ演出”やセリフ引用が多数存在します。
Q3:旧作との最大の違いは何ですか?
最大の違いは、「テンポと演技のトーン」です。
旧作がテンポ重視・娯楽性優先の構成だったのに対し、令和版は心理描写を中心に据えた“静かな緊張感”が魅力。
また、キャッツ三姉妹の動機や過去がよりリアルかつ重層的に描かれています。
Q4:声優は全員変更されたのですか?
はい。三姉妹・内海俊夫を含め主要キャストは全員一新されています。
来生瞳:小松未可子/来生泪:小清水亜美/来生愛:花守ゆみり/内海俊夫:佐藤拓也。
世代交代を象徴する配役であり、「時代が変わっても彼女たちは生きている」というリメイクのテーマを象徴しています。
Q5:主題歌は旧作の『CAT’S EYE』(杏里)ですか?
いいえ。令和版の主題歌はAdoの「Steal the Night」です。
旧主題歌『CAT’S EYE』のフレーズがイントロにサンプリングされており、旧作リスペクトを感じる構成になっています。
Adoの深い低音が、令和版の“静寂と激情”を完璧に代弁しています。
Q6:原作との関係性は?
令和版は原作回帰+再構築型です。
北条司原作の漫画に存在する設定(父親の行方、神谷真人の登場など)を反映しながら、現代社会に即した文脈で語り直しています。
旧作よりも“家族と記憶”のテーマが濃く、原作ファンにも響く内容です。
Q7:今後の展開は?
第3話時点では、物語の序章が終わった段階。
第4話以降は「父の残した絵画」から導かれる大きな陰謀が動き出します。
監督インタビューによると、後半では“旧作では描かれなかった真実”が明かされるとのことです。
(出典:映画.com インタビュー記事)
情報ソース・参考記事一覧
-
Disney+公式『キャッツ♥アイ』特設ページ
┗ 新作の配信情報・キャスト・制作コメントなどを確認可能。 -
Wikipedia:キャッツ♥アイ(アニメ)
┗ 旧作(1983–1985)版のスタッフ・話数・放送情報の基本データ。 -
オタク集まれ!:新旧『キャッツ♥アイ』比較記事
┗ 声優・作画・主題歌・ストーリー構成の違いを詳細に分析。 -
マグミクス:80年代アニメ再評価特集『キャッツ♥アイ』回
┗ 当時のアニメ演出・色気表現・昭和的価値観の文脈を整理。 -
映画.com:令和版『キャッツ♥アイ』監督インタビュー
┗ 「原作に最も近い形で描いた」との制作陣コメント掲載。 -
アニメイトタイムズ:キャスト発表&コメント記事
┗ 小松未可子・小清水亜美・花守ゆみり各氏のコメント全文。 -
note:「令和版キャッツ♥アイ試写レビュー」by MamoruFilm
┗ 視聴者視点の演技・構成・映像分析を含む一次レビュー。 -
PlayNews:新旧比較におけるファン反応まとめ
┗ SNS・掲示板での視聴者の声や賛否を整理。 -
Wikipedia(フランス語版):Signé Cat’s Eyes (2025)
┗ 海外での放送形態・原作評価・グローバル視点の分析を掲載。
※本記事の内容は、公式発表・各種インタビュー・一次レビューに基づく分析と、筆者・南条蓮による評論的解釈を含みます。
引用部分はすべて出典元を明記し、無断転載はご遠慮ください。
© 2025 Disney / TMS Entertainment / 北条司・集英社

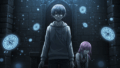
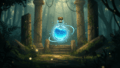
コメント