『ジークアクス(GQuuuuuuX)』──この奇妙な響きに既視感を覚える人は、おそらく「ガンダム」という神話を一度でも通過した読者だろう。
宇宙世紀0085年、シャアがホワイトベースを鹵獲し、ララァの姿なき余韻が”物語の裏”に匂い立つ新作アニメが静かに旋風を巻き起こしている。
本記事では『ジークアクス』という異端のMSと、「いないはずの存在」としてファンの記憶に揺らぎ続けるララァが、本作のどこに“痕跡”として漂っているのか──その構造と感情を解き明かしていく。
ジークアクスとは何か?──物語と機体の正体に迫る
「ガンダムではないガンダム」として登場したジークアクス(GQuuuuuuX)は、視聴者の既知の世界に“裂け目”をもたらした存在だ。
それは宇宙世紀0085年というifの時間軸で、シャアがガンダムを鹵獲し、赤く染めた瞬間から始まる。
この機体と物語に潜む“ズレ”が、ジークアクスの正体をただの主役機以上のものにしている。
宇宙世紀0085年、“もう一つの一年戦争”が始まる
ジークアクスの世界は、ファーストガンダムとは異なる歴史を歩んでいる。
宇宙世紀0085年、ジーンのザクが出撃できなかったことで、代わりにシャアがサイド7へ向かう──そこから歴史は大きく分岐する。
シャアはホワイトベースとRX-78ガンダムを鹵獲し、ジオン軍は圧倒的優位に立つ。
この世界ではアムロは姿を見せず、セイラ・マスが連邦のエースとして活躍し、“女性による英雄譚”が進行していく。
ジオン優勢の改変世界で動き出す赤いガンダム
赤くリペイントされた鹵獲機は、まさに“逆襲のシャア”以前のシャアが手にした幻想的な完成形だ。
この赤いガンダムは、ビット兵器を搭載し、かつてのサイコミュ技術と新たな兵器思想が融合している。
ここに登場する“ジークアクス”は、型式番号gmx-Ω。名称に「ガンダム」の冠が付かないことも、本作が既存の神話を断ち切る意図を感じさせる。
つまりこれは“神話の外”に現れた異形の存在なのだ。
型式gmx-Ω──ジークアクスの特異な構造とサイコミュ操縦
ジークアクス最大の異質性は、そのコックピット構造と操縦システムにある。
操縦者は手のひらを「握り返す」という動作で、まるで“中に誰かがいる”かのような錯覚を覚える。
このインターフェースは、従来のパイロット=兵器という関係性を崩し、「共に動く」存在としての機体を提示する。
しかも、操縦者マチュは民間人であり、彼女が機体を盗み出すことで物語が始まる──この“逸脱”が、本作の全構造に呼応する。
そしてこのサイコミュ系の操縦感覚は、後に論じる“ララァの気配”とも密接に繋がってくる。
ジークアクスという存在は、物語の象徴であると同時に、「再構築されたガンダム神話の継承者」として設計されている。
それはファーストガンダムへのリスペクトであると同時に、明確な“断絶”である。
その境界線の上で、私たちは問い直されるのだ──「それでも、これはガンダムか?」と。
ララァの“気配”はどこにあるのか?──存在しない彼女の残響
『ジークアクス』には、ララァ・スンという名は一度も明言されていない。
だが、その不在こそが、彼女の存在感を際立たせるのだ。
ララァは出てこない。けれど、シャアの言動、サイコミュの描写、機体の挙動、そして“キラキラの向こう側”と呼ばれる概念──すべてが、ララァという幻を引き寄せている。
アムロがいない世界で、ララァの意味は変質する
宇宙世紀0085年の本作には、アムロ・レイの影がない。
彼の不在は単なる設定上の省略ではなく、“ララァの死”という神話的トリガーを喪失した世界を意味している。
ファーストにおけるアムロとララァの関係──ニュータイプ同士の邂逅とすれ違い、そして死──はシャアの運命を大きく決定づけた。
しかし、その物語がそもそも起きていない世界において、ララァは“いない”というより、“まだ生まれていない”のではないか?
この不在の構造が、シャアやマチュ、そしてシュウジの関係性に濃密な“空白”を落としている。
キラキラの彼方に──“ララァがいるかもしれない”という視線
作中で幾度となく登場する謎の概念、「キラキラの向こう側」。
これは視覚演出でもセリフでも語られ、まるで現実と異なる次元、あるいは過去の時間へ繋がる精神空間のように描かれる。
この空間で語られる「誰かが呼んでいる」「懐かしい声がする」といった描写は、明らかにニュータイプ的な感応を示唆している。
ララァの特徴的な存在感──言葉を超えた伝達、温かくも狂気じみた包容力──は、この領域の“声”として潜在しているのだ。
つまり、ララァは記号として存在している。物語にはいないが、精神構造の地層に染み込んでいる。
ララァ不在が浮かび上がらせる、シャアとシャリア・ブルの再配置
本作で最も驚かされたのは、シャリア・ブルが“マブ”としてシャアと関係を持っているという設定だ。
シャリアはかつて『ファースト』で散っていった悲劇のニュータイプだったが、本作では“イケメン化”と“生存”のルートを歩み、シャアと深く繋がっている。
この関係性は、ララァの“後釜”として読めるのか?あるいは、シャアがララァを失わない世界で選んだ新たな心の拠り所なのか?
注目すべきは、ここに明確な恋愛的コードは感じられないことだ。
むしろ“父性”や“友情”、あるいは“自己の影”としてのシャリアという存在が、シャアの心の穴を埋めているように思える。
ララァがいたからこそ崩れたシャアのバランスが、ここでは別の形で支えられている。
このように、ララァの不在は決して空白ではない。
その“残響”は、登場人物たちの関係性、思考、さらには物語構造そのものを通して語られている。
ララァという“いない存在”を、我々はどこまで感じ取ることができるだろうか?
シャア、そしてシュウジ──“生まれ変わり”の寓話
『ジークアクス』を観るうえで、最も不気味で、そして美しい誤解──それが「シュウジ=シャアの生まれ変わり説」だ。
公式に明言されることはない。だが、シュウジの声、言動、そして“赤いガンダム”との距離感は、その仮説を観客の内側で膨張させる。
これは、ただの転生譚ではない。失われた英雄が“語り部”へと変容する寓話なのだ。
「赤いガンダムに乗るシャア」は何を象徴するのか?
本作で最大の衝撃とも言えるのが、シャア・アズナブルが“ガンダムに乗る”という歴史改変だ。
赤く塗られたその機体は、鹵獲されたRX-78。
つまり、シャアはアムロの象徴そのものである“白いガンダム”を奪い、再構築する。
この行為は象徴的であり、彼が“敵”ではなく“主人公”になりうる世界線の可能性を暗示する。
ガンダムに乗るシャアは、もはや「赤い彗星」ではなく、“何かを赦された存在”に見える。
シャアの面影を背負うシュウジ、その声が語るもの
シュウジという青年の存在には、多層的なノイズが乗っている。
彼の口癖、「ガンダムが言っている──」は、まるでかつてのシャアが到達し得なかった“感応の世界”をすでに受信しているかのようだ。
また、声を担当するのが池田秀一氏ではなく、「秀二」なる声優であることも、“二重写しの影”としての演出に一役買っている。
シュウジの存在は、まるで誰かが記憶を「器」として再投影したかのような感触を持つ。
彼はララァの代わりにシャアの心を知る存在であり、かつて“知覚されなかったシャアの心”そのものなのではないか。
ララァの代替となる存在たち──父性、友情、そして“マブ”という距離
シャアの孤独は、いつも誰かの共鳴によって照らし返される。
かつてはそれがララァであり、時にアムロだった。
だが、この世界ではその役割がシャリア・ブルやシュウジへと分配されている。
シャリアとの「マブ」関係は、ララァの持っていた精神的親密性の代替とも読める。
また、シュウジとマチュの関係性にも、ニュータイプ的な共振が見られ、それは「共に世界の真実を見てしまった者同士」の孤独な繋がりだ。
この分岐世界で、“誰がララァで、誰がシャアなのか”という問いは、役割の再分配によって解体されていく。
『ジークアクス』が提示するのは、転生の物語ではない。
これは“神話を語り直す者たち”の物語である。
そしてその語り直しは、シャアの面影に憧れる者──我々ファンの姿にどこか似ている。
視聴者を撃ち抜く“Beginning”パートの構造
『ジークアクス』の幕開けは、観客の意識を“別の時間軸”へ強制的に連れて行く儀式のようだった。
冒頭、ファーストガンダムのナレーションとBGMが流れた瞬間、誰もが「知っているはずの物語」が始まると錯覚する。
しかし、その安心はすぐに崩れ去る。
第一話ナレーションとBGMから始まる“もう一つの開戦”
「宇宙世紀0079年──」と響くナレーション、ホワイトベースの発進、ザクの接近。
この“再現”のような序盤に、観客はほぼ条件反射的に「ファーストだ」と納得してしまう。
だがそれは、仕掛けられた「罠」だった。
ジーンのザクが出撃できなかったことで、物語は急転。
代わりにシャアが偵察に向かい、ガンダムとホワイトベースをジオンが鹵獲するという“ifの開戦”が始まる。
このねじれこそが『ジークアクス』最大の醍醐味であり、観客の記憶と構造を裏切ることで物語の正体を問うてくる。
「ジーンの不在」で動き出した歴史のズレ
すべての始まりは、ジーンのザクが整備中で出撃できなかったという、たった一つのズレだった。
この微細な“if”が、シャアという存在の位置付けを変え、アムロの登場を無にし、セイラを英雄に据える世界を生んだ。
この改変は、「キャラクターの運命」をテーマとするガンダム作品群の中でも、最も露骨で実験的なものだ。
なぜなら、「歴史はほんの一つの歯車で変わる」という事実を、これほどまでに痛快に描いた作品は他にないからだ。
観客はそのズレを“発見する側”ではなく、“被害者として体感する側”に置かれている。
庵野秀明×米津玄師──文脈と音が重なるオープニング
この“Beginning”パートを脚本で担っているのは、庵野秀明。
そして主題歌「Plazma」を歌うのは米津玄師。
彼らの起用は単なる話題性ではない。文脈のレイヤーとして極めて緻密に機能している。
特に「Plazma」二番の歌詞は、マチュとシュウジが出会う“改札の描写”と完全にシンクロしており、物語と音楽が一体となって「もう戻れない運命」を可視化している。
このようにして、『ジークアクス』は序盤から“知っている物語”を“知らない現実”に書き換える衝撃をもたらす。
それはガンダムであると同時に、もはや“ガンダムではないもの”の始まりなのかもしれない。
記憶を裏切ることから始まる物語──それが、『ジークアクス』の「Beginning」だった。
これは追体験ではなく、“再定義”という衝撃の告白なのだ。
ジークアクスとララァが描く、ガンダム神話の再構築
『ジークアクス』は、ただの“if設定”にとどまらない。
むしろ、これまで蓄積されてきたガンダムという神話体系を根本から書き換える試みだと言える。
ジークアクスという異形のモビルスーツと、“いないララァ”の残響が交差するこの物語には、再構築=神話の分解と再接続という意志が明確に込められている。
ファーストガンダムの記憶を背負い、脱構築する構造
ジークアクスは、あらゆる面で「既存ガンダム像」に対する問いかけを持っている。
型式番号gmx-Ω、名称に“ガンダム”を冠しない主役機、民間人による奪取、そしてニュータイプを前提としない操縦法。
これらの要素は、ファーストで構築された“ガンダムとは何か”という定義に対し、一つずつノーを突きつけていく。
そのうえで、作中の演出やセリフ、世界観にはファーストガンダムへの濃密なオマージュが散りばめられている。
つまり本作は、ガンダム神話の否定ではなく、「脱構築=再接続」によって未来の神話を打ち立てようとしているのだ。
“魂の継承者”としてのマチュとその狂気的魅力
マチュというキャラクターは、“ガンダムに乗る少女”というだけではない。
彼女は“なぜかジークアクスを動かせてしまう”存在として描かれ、ニュータイプ的な資質を自然と受け継いでいるように見える。
だがそれは、「特別な才能」ではなく、「世界に染み込んだ記憶」へのアクセスのように思える。
飛び込み台の最上段で逆立ちをする、制服のままMSを操る、シュウジの声に微笑む──どこか人間らしくない、でも美しい彼女の振る舞いは、ララァの魂が現代に降り立った姿にも見える。
マチュは象徴的な存在であり、「ジークアクスと通じる者」として、物語の精神的な中心にいる。
ララァという“記号”が繋げる時空と存在の断片
ララァがいないにも関わらず、彼女の気配が常に漂っている理由。
それは、ララァという存在が“キャラクター”ではなく、“記号”として作品の空間に刻まれているからだ。
「サイコミュ」「ニュータイプ」「共振」「別の次元」「キラキラの向こう側」──これらはすべて、ララァという“語られなかった中心”に紐づけられていく。
シャアの変質、シュウジの内面、マチュの挙動。
すべては“語られていないララァ”を通してつながっている。
彼女は存在しないが、あらゆる中心にいる。
その構造こそが、ガンダムという神話の本質なのではないか。
『ジークアクス』は、ララァを消すことでララァを甦らせている。
そしてその語り方は、いまこの時代に再びガンダムを語るための“更新”なのだ。
ジークアクスとララァが織りなす、新たな神話へのまとめ
『ジークアクス』がここまで語ってきたのは、機体の性能でもキャラの活躍でもない。
それはむしろ、記憶と神話の“再配置”だった。
ララァは登場せず、アムロもいない。シャアは変質し、物語そのものが観客の記憶とズレを生じさせる。
だが、だからこそ──“語られなかったもの”への想像力が、作品の中に生き始める。
アムロもララァもいない世界で、我々は何を見るのか
アムロ・レイという“主人公”の不在は、これまでのガンダム作品では考えられなかった構造だ。
その穴を埋めたのがセイラであり、マチュであり、シュウジであるという点に、『ジークアクス』の新しさがある。
この物語はもはや「英雄譚」ではない。
“英雄を失った世界”で、どう語りを紡いでいくかという試みなのだ。
そしてそこには、ララァという「語られなかった人物」こそが最も深く根ざしている。
“語られない存在”こそが、この物語を動かしている
ララァがこの作品の中で果たしているのは、「不在という存在感」だ。
観客の中に記憶があるからこそ、そこにララァを“見る”ことができる。
これは単なるファンサービスでもノスタルジーでもない。
むしろ、『ジークアクス』はガンダムの神話性を現代的にアップデートするために、“語られない存在”に語らせるという構造を選んだのだ。
その結果、登場人物たちの行動や選択が、見えない何か──すなわち“ララァ的なるもの”に導かれているように見えてくる。
だから今、ジークアクスは「ガンダムが言っている」と囁く
劇中で繰り返される、シュウジのセリフ。
「ガンダムが言っている──」
この意味深な言葉は、機体が意志を持っているというだけでなく、“記憶そのものが語りかけてくる”感覚に近い。
そこにはシャアの記憶、アムロの不在、ララァの残響がすべて混ざり合い、ジークアクスを通して再構成される。
『ジークアクス』とは、“新たな神話”の名である。
それは、「かつて語られた物語」をもう一度手に取って、今この時代の言葉で紡ぎ直す試みなのだ。
そして私たちはその神話の“目撃者”として、あの名セリフを改めて噛みしめる。
──「ガンダムが言っている」。
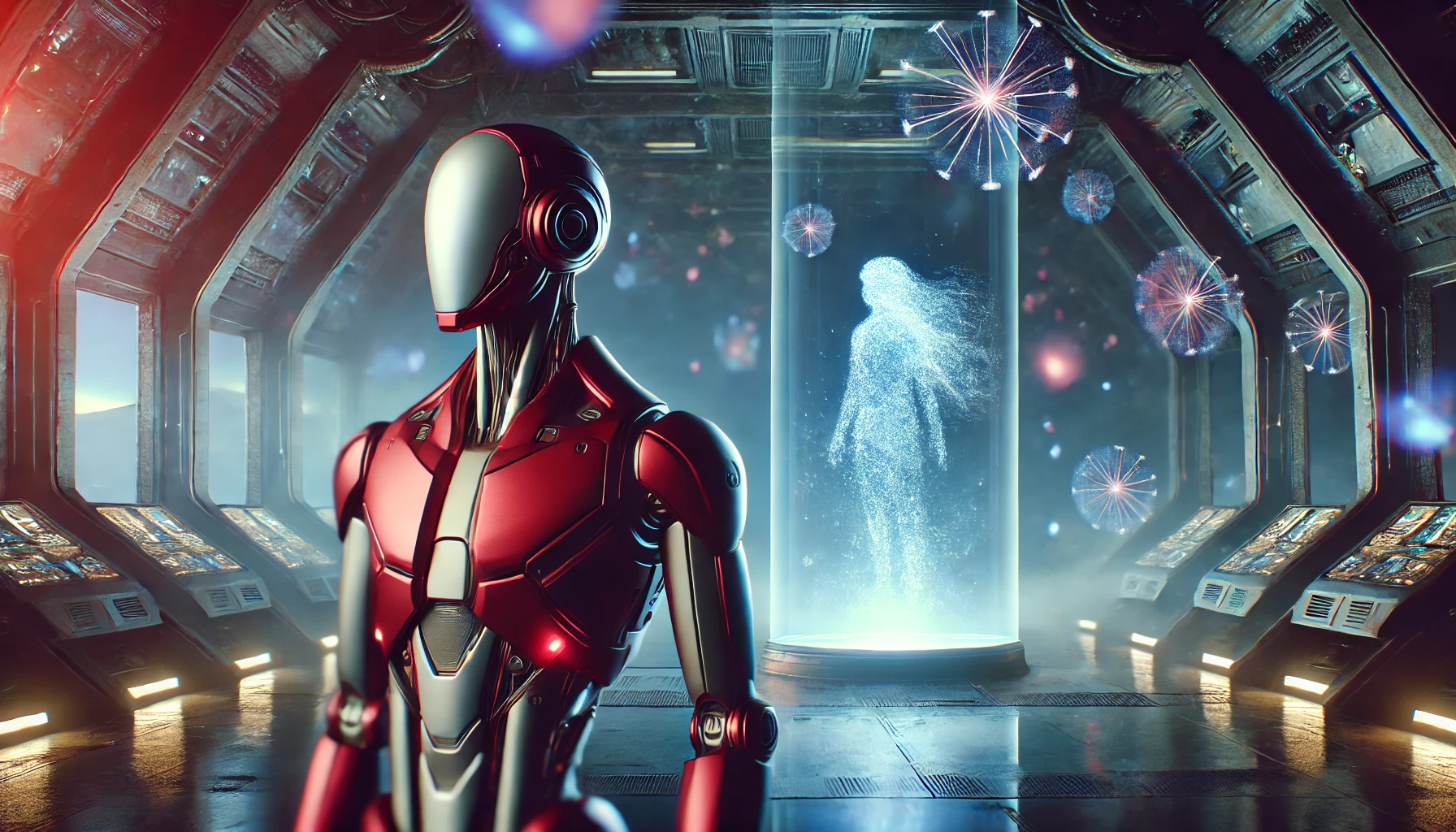


コメント